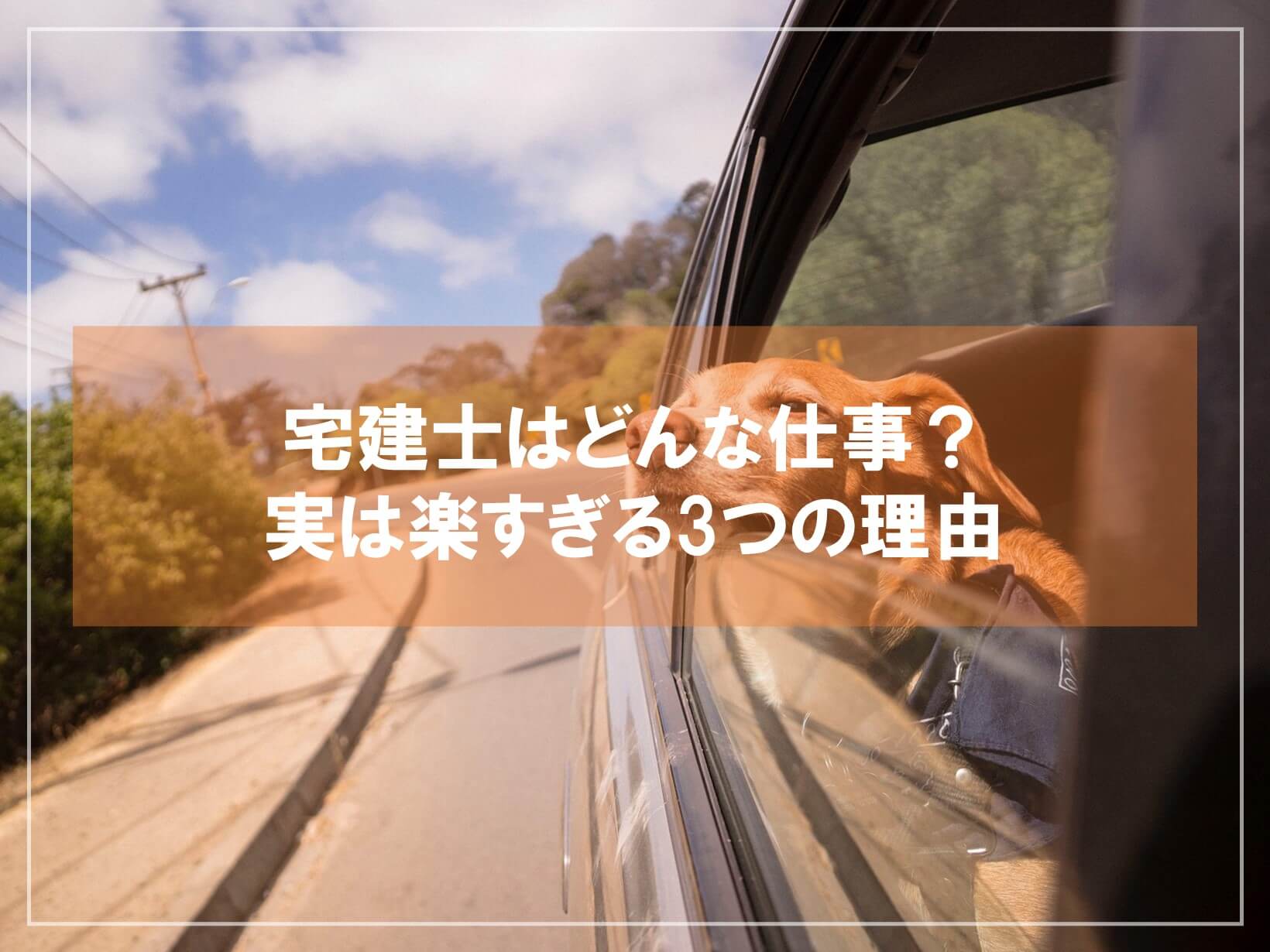宅建試験に一発合格し不動産業界で数年勤めた経験もある杉山貴隆です。
今回は宅建士の仕事について次の3点を語ります。
- そもそも宅建士の仕事内容とは?
- 宅建資格を持っていると役立つ職種とは?
- 宅建士の仕事が楽すぎる理由3つ
私が不動産業界で目にしてきた事実をもとにお伝えします。「宅建士の資格を取って楽な仕事をしたい…!」と考えている方にはきっと参考になるはずです。ぜひ最後まで読んでみてください。
宅建士の仕事がわかる本は?の項目を加筆しました。中央経済社の『こんなにおもしろい宅地建物取引士の仕事』を一読したので、その紹介です。
宅建士の仕事内容とは
宅建士の仕事内容は宅建資格者に認められている3つの独占業務が主体となります。
- 重要事項説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
- 契約書(37条書面)への記名押印
以下で詳しく解説します。
重要事項説明
重要事項説明とは不動産をこれから買おうとする人(買主)や借りようとする人(借主)に対し契約に関係する重要事項を事前に説明する業務です。省略して重説とも言います。
たとえば営業担当者がお客様を物件に案内した後、契約する気になったお客様と一緒に戻ってきたとします。お客様が申し込みに至った場合、宅建士はお客様に宅地建物取引士証を提示して重要事項を口頭で説明します(日を改めて説明することもよくあります)。
重要事項とはどんなものでしょうか。たとえば次の項目が重要事項に該当します。
- 対象不動産の登記簿上の所有者
- 契約の解除に関する事項
- 台所・浴室・便所その他の設備の整備状況(賃貸借物件の場合)
上記以外にも多岐にわたる項目があるため、宅建士が全て暗記して説明することは不可能です。なのであらかじめ重要事項説明書を印刷して手元に置き、お客様にも1部手渡して読み上げるという形で説明を実施します。
重要事項説明書(35条書面)への記名押印
重要事項説明書(35条書面)への記名押印とは重要事項説明書に対し宅建士が記名し自身の印を押す業務です。
重要事項説明書は営業担当者が作る場合もあれば宅建士が作る場合もあります。どちらの場合も最終的には宅建士がその内容を確認します。そして法令上の問題が無いと判断できたら「確認完了しました」という意味合いで宅建士が記名・押印します。
もし重要事項説明書の内容が誤っていて、それに気づかずに記名押印してしまうと、後でトラブルになって宅建士の責任が問われることになります。最悪の場合は訴訟を起こされて損害賠償責任を負うこともありますので、かなり気を使う業務です。
契約書(37条書面)への記名押印
契約書(37条書面)への記名押印とは契約書に対し宅建士が記名し自身の印を押す業務です。
契約書も重要事項説明書と同様、営業担当者が作る場合もあれば宅建士が作る場合もあります。契約書は数十、場合によっては百を超える条文から成りますが、最終的にはその1つ1つを宅建士がチェックします。
内容に法令上の問題が無いと判断できたら「確認完了しました」という意味合いで宅建士が記名・押印します。もし契約書の内容に問題があるのにそれに気づかず記名押印してしまうと、後でトラブルになって宅建士の責任が問われることになります。
契約書は極めて重要度が高い書面ですので、その記名押印は重要事項説明書以上に神経をすり減らす業務です。
宅建資格が役立つ職業とは
宅建士の仕事内容を踏まえた上で宅建資格が役立つ職種にはどんなものがあるでしょうか。特に役立つ職種は次の3つです。
- 宅建事務
- 営業職
- 不動産管理職
以下で詳しく説明します。
宅建事務
宅建資格を活かせる職種の最も代表的なものは宅建事務です。宅建事務はその名の通り宅建資格を持った事務員をイメージしてください。
事務職として社内のさまざまな事務をこなしつつ、営業担当者がお客様を連れて戻ってきたときは宅建士としての業務(重説など)を行います。宅建事務は宅建資格を持ったオバちゃんやお姉さんがやっていることが多いです。
営業職
宅建資格を活かせるもう1つの職種は営業職です。ここまでの説明では「営業担当者がお客様を連れてきて、宅建士が重説をする」というシーンを前提にしてきましたが、優秀な営業マンの中には宅建資格を持っている人もいます。
宅建資格を持っている営業マンは重要事項説明や書面のチェックを自分以外の人に依頼しないで済むので効率的です。お客様としても、それまでやりとりしてきている営業担当者に重要事項を説明してもらうことで安心して契約に進めます。
以上のことから売買仲介や賃貸仲介においては営業担当者が宅建資格を持っているのが理想的と考えられています。不動産会社が営業担当として就職した人に半ば強制的に宅建試験を受けさせることがあるのはこのためです。
とはいえ不動産の営業マンは残業・休日出勤も多いため、コツコツ勉強して宅建試験に合格するのはかなり難しいです。ゆえに営業マンが宅建士を兼ねることは多いとは言えません。
不動産管理職
宅建事務・営業以外で宅建資格を活かせる職種として不動産管理職があります。不動産管理会社のスタッフです。
不動産管理会社はオーナー(大家)の委託を受けて賃貸物件を管理しています。管理そのものには宅建士の業務は不要なのですが、不動産管理会社はオーナーの委託を受けて貸主の立場を代理して賃貸契約を締結することが多く、その際に宅建士が活躍します。
つまり不動産管理会社において宅建資格を持った従業員は通常は管理物件を巡回して設備の状況を確認したりしているのですが、他社(不動産賃貸仲介業者など)が入居希望のお客様を見つけたときは宅建士としての業務を行う、ということです。
不動産管理会社の管理スタッフは私のイメージではオジさんがやっていることが多いです。ちなみに私も不動産管理会社で管理業務+宅建士をやっていました。
宅建士の仕事が楽すぎる理由
上で紹介した3つの職種のうちおそらく最も人数が多いのは宅建事務です。そして宅建事務を前提にすると正直、宅建士の仕事は楽です! 宅建士(宅建事務)の仕事が楽な理由は次の3つです。
- ノルマに追われない
- 定時に出社・退社できる
- 給料や年収も悪くない(手当あり)
以下で詳しく見ていきます。
ノルマに追われない
宅建士(宅建事務)の仕事が楽な理由の1つめはノルマに追われないことです。事務系職種なので当然と言えば当然ですね。
宅建士(宅建事務)は営業職の男性スタッフがノルマ未達で上司に詰められているのを横目に見て「かわいそう…」と感じつつ「でも自分には関係ない」と思っていたりします。笑
定時に出社・退社できる
宅建士(宅建事務)の仕事が楽な理由の2つめは定時出社・定時退社が可能なことです。これも事務系職種なので当然と言えば当然でしょうか。
もちろん繁忙期(年度の変わり目など)には残業が必要になることもあります。でも普段していない残業をしているのですから、当然残業手当はもらえます。
宅建士(宅建事務)は営業職の男性スタッフが早朝出社・サービス残業に苦しんでいるのを横目に見て「かわいそう…」と感じつつ「でも自分には関係ない」と思っていたりします。笑
給料や年収も悪くない(手当あり)
宅建士(宅建事務)の仕事が楽な理由の2つめは給料・年収が悪くないことです。事実、先日行った当ブログの調査では宅建事務の平均年収は425万円でした。
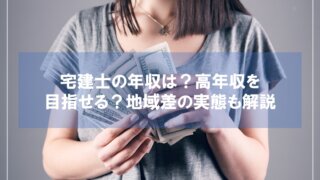
特に宅建事務は宅建手当といって務めている不動産会社の専任の宅建士を務めることで1万円~数万円の手当が出ることがよくあり、給与が高くなります。ノルマ無し、定時出社・退社可でお金もたくさんもらえるんです。
宅建士(宅建事務)は安月給でこき使われている営業職の男性スタッフを横目に見て「かわいそう…」と感じつつ「でも自分には関係ない」と思っていたりします。笑
宅建士の仕事がきつい人もいる
ここまでは「宅建士の仕事は楽」とお伝えしてきましたが、それは宅建事務として働く場合です。宅建事務ではなく宅建資格を持った営業職や宅建資格を持った不動産管理職をしている人なら「仕事がきつい」と感じてもおかしくはありません。
宅建持ちの営業職がきつい理由
宅建資格を持った営業職になると、自分の契約を処理していくだけでも忙しいのに他の営業マンから重説やら何やらを頼まれて、そちらの業務にも追われることになります。
「えっ 他の営業マンの重説は宅建事務の人がやってくれるんじゃないの…?」
と思った方。するどいですね。確かに原則はそうです。しかし宅建事務の人は定時に帰ってしまうことを忘れてはいけません。つまり定時以降の宅建士の業務は全て宅建持ちの営業担当者に降りかかってくるのです。メチャクチャきついです…!
宅建持ちの不動産管理職がきつい理由
宅建資格を持った不動産管理職がきつい理由も同じです。自分の管理業務で忙しいのに、社内の仲介部門の営業マンに重説等を頼まれて時間をとられてしまうのです。
もちろん日中はいろいろな物件を巡回するのでそういうことはありません。問題は宅建事務が帰ってしまった夜の時間帯。
案内を済ませてお客様を連れて帰ってきた営業マンに「重説をお願いします…」なんて言われたら、むげに断ることもできません。
お客様対応を終えて自分の仕事に取り掛かる頃には21時を過ぎています。そこから自分の残務を処理したら22時、23時…となるわけで、仕事がきついと感じたとしても無理はないでしょう。
楽をするための注意点
宅建士として楽をするためには宅建資格を持った営業職・不動産管理職になってはダメです! 日常的に長時間労働となり、ワークライフバランスが滅茶苦茶になってしまいます。
仕事が楽であることを重視するなら、業務過多になりがちな「宅建資格を持った営業職・不動産管理職」を目指すべきではありません。
* * *
とはいえ「宅建資格を持った営業職・不動産管理職」は仕事が大変なぶん、宅建資格を持たない社員から尊敬や信頼を集めたり、感謝されたりします。
それに「宅建資格を持った営業職・不動産管理職」は会社から見ても理想的な人材なので、将来の収入アップや昇格が期待できるといった良い面もあります。
楽ばかりを追い求めるのではなく、やりがいや将来性を含めて考えるなら「宅建資格を持った営業職・不動産管理職」も狙うべきポジションの1つです。
よくある質問
ここからは宅建士の仕事に関するよくある質問に答えます。
宅建士の仕事は未経験でもできる?
宅建士の仕事は専門性が高いので、未経験でもできるのだろうかと心配になりますよね。結論を言うと未経験可の募集であれば、応募し入社するところまでは可能です。
ただし業務の細かい部分については経験のある先輩から教えてもらう必要があるでしょう。先に宅建士の独占業務を3つ紹介しましたのでその順に少し解説します。
- 重要事項説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
- 契約書(37条書面)への記名押印
上記のうち重要事項説明はほぼ読み上げるだけなのでそう難しくはありません。その一方、重要事項説明書への記名押印は書面のどんな点をチェックすればいいのかといった実務的なところは先輩社員に教えてもらう以外にないと思います。
重要事項説明書を作成するところから任される場合もあります。その場合はなおさら教えてもらわなければできません。
契約書への記名押印についても同様です。チェック箇所や作成方法の手ほどきを受ける必要があるでしょう。
とはいえ最近はYouTubeで重要事項説明書・契約書の作り方を学ぶこともできたりします。
宅建士の仕事は40代・50代・60代でもできる?
宅建士の仕事は40代・50代・60代でも可能です。体力を使う仕事ではなく、考える力や専門知識を使う仕事ですので。求人状況は検索で調べてみるといいでしょう。
宅建士の仕事に英語は必要?/英語求人はある?
宅建士の仕事に英語力は基本的に不要です。街の不動産屋や一般的な不動産会社に勤めるにあたって英語力が求められることはまずありません。
とはいえ近年は外国人の移住者が増えていることもあり、英語力を持った宅建士の求人が出ることもあります。宅建資格と英語力の両方を兼ね備えていれば年収も上がりやすいです。
英語力を活かせる宅建士求人を探したい方は「宅地建物取引士 TOEIC」で求人サイトを検索してみてください。
「英語」ではなく「TOEIC」というキーワードがおすすめです。「英語」をキーワードにすると「英語力不問」という求人ばかり出てきてしまいますので。
建築士と宅建士の仕事の違いは?
建築士は建物を設計することが主な仕事です。建築士は建物の設計図を作るための専門知識を持っていて、実際に設計図を書くこともできます。
これに対し宅建士は建物(あるいは土地)を「売りたい・買いたい」「貸したい・借りたい」という人がいるときに、スムーズかつ適正に取引がなされるようサポートするのが主な仕事です。宅建士は建物や土地の契約に関する専門知識を持っていて、実際に契約を進めていきます。
以上をまとめると、建築士は設計図を書く。宅建士は契約をサポートする。社会において果たす役割は結構違います。
宅建士の仕事がわかる本は?
山瀬和彦著『こんなにおもしろい宅地建物取引士の仕事』をお勧めします。
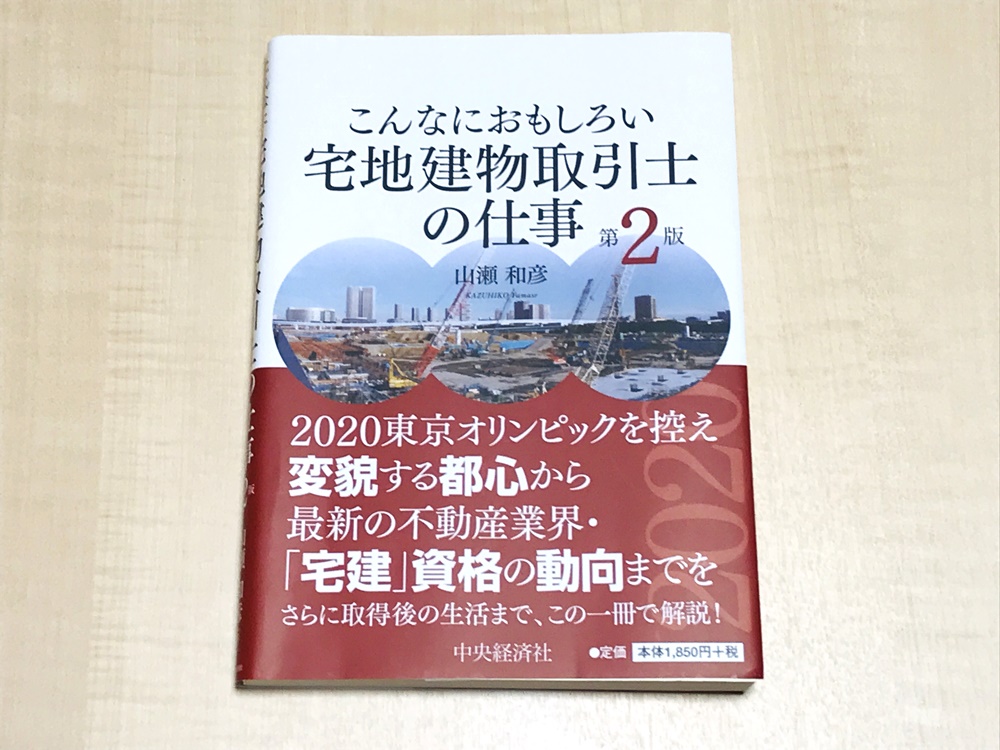
著者は資格対策予備校で宅建講座の講師を務めた後に不動産業界で独立した方です。このような経歴の人はいそうですが意外といません。宅建試験のプロでありながら不動産業のプロでもあり、宅地建物取引士の仕事について書くなら絶対にこの人が適任だと感じます。
本書の目次は次の通りです。
序章 近年の不動産取引に関連する事件
第1章 面白い資格「宅建取引士」
第2章 「宅建取引士」とは
第3章 宅建取引士の歴史
第4章 不動産業で「宅建取引士」は開業できるか
第5章 宅建取引士の主要業務(重要事項の説明)
私も個人的に購入し一読したのですが、かなり良いと思いました。宅建試験の概要や攻略法はもちろん、不動産業界の内部事情、稼ぎ方、そして業界人としての建前を述べつつ、本音も大いにぶっちゃけています。
これから宅建の資格をとって不動産業界で働こうと考えている人が読むと、宅建士になるまでの道筋とその後の働き方について具体的なイメージが持てるはずです。ぜひ一度読んでみてください。
(なお本書の前半部分に80~90年代の法律系専門学校の動向みたいな話があります。その箇所を読むと人によっては「どうでもいい」と感じて読むのをやめたくなるかもしれませんが、全体的には良書です。そこだけ飛ばして残りを読み進めましょう。)
この記事のまとめ

今回は宅建士の仕事について詳しくお伝えしました。この記事の要点を復習すると次の通りです。
- 宅建士の仕事内容とは
- 重要事項説明
重要事項説明書(35条書面)への記名押印
契約書(37条書面)への記名押印 - 宅建資格を持っていると役立つ職種
- 宅建事務
営業職
不動産管理職 - 宅建士(宅建事務)の仕事が楽すぎる理由
- ノルマに追われない
定時に出社・退社できる
給料や年収も悪くない
注意点として、宅建資格を持つ営業職・不動産管理職になってしまうとなかなか楽ができません。ただそのぶんキャリアとしての価値はあるので、あえてその道を選ぶのも悪くはないでしょう。
いずれにしても宅建資格が手に入れば選択肢が広がります。長い人生の各段階で自分に合った働き方を選ぶためにもぜひ宅建を取りましょう。
以上、参考になれば嬉しいです。