宅建試験に一発合格した宅建士杉山貴隆です。
宅建資格の取得を検討している人が最も気になることの1つは「宅建って就職に役立つの?」ということだと思います。そこで今回は宅建取得後の就職事情についてお伝えします。取り上げる話題は主に以下の3点です。
- 宅建資格を持っていると就職活動で有利になる理由
- 主婦・未経験者・高卒者・中卒者の就職に宅建資格が与える影響
- 求職者の年齢によって宅建資格の効果は変わるのか
就職が有利になるなら宅建試験を受験したい。実際のところどうなんだろう? そんな疑問・迷いはこの記事を読んでいただければ解決します。ぜひ参考にしてみてください。
不動産業界への転職を考えている方は宅建Jobエージェントに登録しておきましょう。
宅建Jobエージェントは不動産業界に特化した完全無料・全国対応可の転職支援サービスです。業界経験者はもちろん、未経験の方・宅建未取得者の方もキャリア相談できるので、新規登録者は毎月2,000人以上。
早めにあなたの希望を伝えておけば、最適な求人が出たタイミングで連絡をもらえます。業界最新の求人情報を見逃さないために今日から登録しておくのがお勧めです。
宅建とは?宅建士とは?
宅建とは日本の国家資格のひとつで、正式名称を宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)といいます。宅建資格を持っていると不動産取引に関する法律のプロであることを証明できます。
不動産は非常に高額なので不正な取引が行われないようにさまざまな法律が定められています。そういった不動産取引関連の法律を熟知している人に与えられるのが宅建という資格なんです。
宅建の資格を持っている人のことを宅建士(たっけんし)といいます。厳密に言うと「宅建試験の合格者として氏名等を都道府県に登録した人」を宅建士と呼びます。
宅建取得者の就職が有利になる理由
宅建資格を取得すると就職活動では断然有利になります。宅建があれば仕事には困らない・一生食いっぱぐれないとまで言われるほどです。その理由は色々ありますが、整理すると以下の3つになります。
- 不動産会社では宅建士が「5人に1人」以上必要だから
- 一定の法律知識を有することの証明になるから
- 頑張れる人だとわかるから
以下で詳しくみていきましょう。
不動産会社では宅建士が「5人に1人」以上必要だから
宅建資格取得者が就職で有利になる理由の1つめは不動産会社では5人に1人以上の割合で宅建士が必要だからです。
日本では宅建業法という法律により「宅建業者は従業員の5人に1人以上の割合で宅建士を雇いなさい」と定められています。これは不動産会社等に不動産取引関連の法律を守らせるためです。あなたの街のどの不動産屋さんにも宅建士が必ず在籍しています。
5人に1人以上を有資格者にする義務は企業側からするとかなり厳しい要求です。こういった規制があるため不動産事業を営む会社は常に宅建資格を持った人材を求めています。そのため宅建取得者はそうでない人よりも就職しやすいと言えます。
一定の法律知識を有することの証明になるから
宅建資格取得者が就職で有利になる理由の2つめは一定の法律知識を有することの証明になるからです。
現代はコンプライアンス(法令遵守)の時代だとよく言われます。コンプライアンスとは「企業は法律やルールを良く守って営業活動をしなければならない」とする考え方のことです。
SNSが普及した現代ではコンプライアンスが守れていない会社は従業員や顧客によってネット上で告発されることがあります。告発により悪い評判が広まってしまうと大損害につながるため、企業のコンプライアンス意識は近年これまでになく高まっています。
社内の従業員の順法意識を高める観点をとるなら、ある程度法律の知識を持っている人材を採用しておくほうが社内で不正が起きにくくなり、告発が起きるリスクを下げられると考えられます。
ここで宅建資格は法律に関する資格だということを思い出してください。宅建取得者は消費者保護や民法について学んできており法令遵守の意識が高いことを期待できます。このことから宅建資格を持っている人はそうでない人よりも就職しやすくなっています。
頑張れる人だとわかるから
宅建資格取得者が就職で有利になる理由の3つめは頑張れる人だとわかるからです。
宅建試験の合格率は例年15%前後です。10人が受験しても8~9人が不合格になる試験であり、そう簡単には合格できません。合格するためには学習計画を立て、コツコツと努力を続ける必要があります。
ということは企業から見れば宅建取得者は「計画性があって努力を継続できる人」つまり「頑張れる人」だと評価できます。
宅建くらいでそこまで考えてくれるかな?と疑問に思うかもしれませんが、人事経験の長い人ほど宅建試験合格の価値は認識しているものです。以上の理由から宅建資格を持っている人はそうでない人よりも就職しやすくなっています。
宅建士の就職先
宅建取得者の就職先について不動産業界とそれ以外とを順番に見ていきましょう。
不動産業界
宅建資格を取った後は不動産業界全般が就職先になるのですが、その中でも特に次の業種が就職先になりやすいです。
- 不動産売買仲介業
- 不動産賃貸仲介業
- 住宅の建売業(ハウスメーカー)
不動産の売買や賃貸の仲介、建売住宅の売却に際しては重要事項説明等の宅建士にしか認められていない業務を実施する必要があります。そのため上記の業種では宅建資格を持つ人のニーズが特に高いです。
不動産業界のその他の業種としては以下のものがあります。
- 不動産管理業
- 不動産賃貸業(大家業)
- 不動産鑑定業
- 建設請負業
これらの業種においては、もしその事業に特化するのであれば宅建士は必ずしも必要とされません。そのため先に示した売買・賃貸の仲介業や建売業に比べれば宅建資格を持つ人のニーズは低いです。
とはいえ不動産管理業・不動産賃貸業・建設請負業を営む会社は宅建士を必要とする業務(仲介や建売)も合わせて行っていたり、今はやっていなくても今後はやりたいと考えていることが多いため、これらの業種においても宅建資格を持っていれば就職しやすいと言えます。
不動産業界以外
不動産業界以外で宅建士が求められるのは主として金融業界です。
銀行や信用金庫が大きなお金を貸すときは借りる人の土地や建物を担保にとります。そのため不動産や不動産取引の専門知識を有する人材のニーズが高く、数多くの宅建取得者を雇用しています。
宅建資格はこんな人の就職も有利にする
宅建資格は主婦・未経験者・高卒者・中卒者の就職も有利にします。
主婦の就職
主婦が仕事を得ようとするとき、宅建を取得していると就職が有利になります。不動産会社では宅建資格を持った女性事務員を必要としていることが多いためです。
宅建事務という職種名でよく募集がかかります。機会があれば求人サイトで宅建事務というキーワードを検索してみてください。たとえ子育てのために数年間のブランクがある主婦の方であっても、宅建資格を持っていれば宅建事務の担当者として採用されやすいです。
ちなみに当ブログの調査では宅建事務の平均年収は425万円でした。事務職としてはかなり魅力的な数字ではないでしょうか。
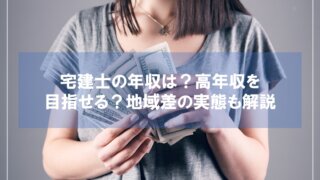
宅建の資格を活かして社会復帰したい女性の方は子育て中の女性が宅建士の資格を取る最良の方法の記事も読んでいただければと思います。
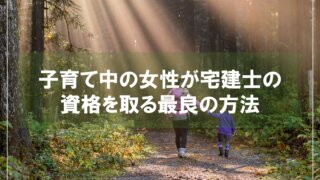
子育て中・子持ちの方に向けて書いた宅建の勉強法の記事です。上の記事を参考に宅建試験の合格を目指してください。
未経験者の就職
不動産業界はもともと未経験者であっても入りやすい業界ですが、宅建資格を持っていればいっそう採用されやすくなります。
その理由は先にも触れたように不動産会社では従業員5人に1人の割合で宅建士を雇う必要があり、宅建資格を持っていることで一定の法律知識を有することが証明されるうえ、頑張れる人だとアピールできるからです。
実を言うと私も宅建取得後、経験が全くなかった不動産管理会社に入社できたほか、IT業界や大手メーカーなどへの転職に際しても宅建資格をアピールし、内定獲得に成功してきました。その経験から宅建は未経験者を大いに助けてくれる資格だと確信しています。
高卒・中卒の就職
宅建資格は高卒者や中卒者の就職もしやすくしてくれます。
そもそもなぜ学歴の高い人は就職に強いのでしょうか? それは彼らに「大卒」というラベルがあるからです。履歴書に「○○大学 卒業」と書かれていれば賢そうに見えます。実際に優秀かどうかはともかく、実務もよくできそうに見えるので採用されやすいのです。
高卒者や中卒者は大卒ラベルを持っていませんので代わりのラベルを持っておくべきです。そして宅建資格は「代わりのラベル」として大いに機能します。
宅建資格はそもそも大卒者であってもそう簡単には合格できません。それどころか大学によっては宅建の取得を目指す「不動産学部」なんてのがあったりするくらい。専門的な勉強をしなければ取れない資格なのです。
だから宅建というラベルを持っていれば企業の人事担当者の目にはあなたが魅力的に映ります。忍耐強く学べる人だと評価してもらえますし、思考力を持った人物だと感じてもらえるはずです。ぜひ宅建試験の合格を目指してみてください。
「でも宅建試験って難しいらしいから自分には無理なのでは?」 そう思う方は高卒者が宅建を取れる理由の記事を読んでください。どんな勉強をすればいいのかわかります。中卒の方にも参考になると思います。

宅建資格取得者の年齢と就職
宅建の資格を持っていると就職にどのような影響があるのかを年齢別に解説していきます。
20代~30代の就職
20代から30代の方は宅建資格を持っていると就職が非常に有利になります。
実際に私自身20代後半から30代前半にかけて数回の転職に成功しました。たいしたキャリアも無いのに不動産管理会社に採用してもらえたり、IT企業やメーカーなどにも正社員として転職できました。それを可能にした大きな要因が宅建でした。
履歴書の資格欄に「宅地建物取引士試験 合格」と書いてあると非常に目立つようで、どの企業に面接に行ってもこの資格のことに言及がありました。
人事担当者は宅建がそれほど簡単に取れる資格ではないと理解しています。ゆえに宅建に合格していることで10人に1~2人の人材として評価してもらえます。20代・30代の方には宅建資格の取得はかなりおすすめです。
40代~50代の就職
宅建資格は40代から50代の方の就職もある程度有利にしてくれます。
といいつつ40代から50代ともなると宅建の影響力は相対的に小さくなることも間違いありません。いわゆるミドルの年齢になれば「これまでにどのような領域でどんな実績を上げてきたのか」というキャリアの側面のほうが重視されやすいからです。
そのため特に不動産関連業以外の業界では宅建の効果は小さくならざるを得ないでしょう。これに対し不動産関連業(不動産・建設・金融など)では宅建資格は有効に機能します。
法律の専門知識を有していることの証明になりますし、従業員5人に1人の設置義務の観点からも企業としては欲しい人材だからです。
以上のことから40代・50代の方の場合は不動産関連業界内での転職、あるいは他業種から不動産関連業への転職であれば、宅建資格を持っておく価値が高いと言えます。
60代~高齢者の就職
宅建資格は60代やそれ以降の高齢者の方の就職もやや有利にしてくれます。シニアの就職の実態はミドルの人以上にこれまで積み上げてきたキャリアが重視される側面があり、宅建資格の影響はかなり小さいと言わざるを得ません。
ただしそれはその年代のハイクラス求人の場合です。ハイクラス求人ではない比較的軽めの仕事を求めている場合は宅建資格は力を発揮します。
なぜなら20代・30代の人であっても宅建資格を持たない人のほうが圧倒的多数だからです。60代でも宅建を持っていればその希少性に価値が生まれます。もし企業が宅建取得者を強く望んでいる場合は、たとえ年齢が60歳を超えていようとも宅建を持っている人に魅力を感じます。
60代以上の方にはそれまでの豊かな経験もありますので、宅建資格を自身の経験と関連付けつつ強みとしてアピールするのが効果的です。
よくある質問
宅建と就職に関するよくある質問に答えます。
大手への就職も有利になる?
宅建資格は大手への就職においても有利です。なぜなら先に触れたように一定の法律知識を有することの証明になるからです。
大手であればあるほど自社が持っている信用が毀損(きそん)することを恐れます。上層部が把握していない社員レベル・部門レベルで不正が行われ、それがSNS等を通じて告発・炎上となれば、信用が毀損されて大損害を被ってしまいます。
そういうことが起こる可能性を小さくするには法律について一定の知識を有し法令遵守の意識が高い人材を雇うことが一番です。この観点から大企業への就職においても宅建資格を持っていることが良い影響をもたらしてくれます。
就職後の年収は?
宅建を活かした就職によって得られる平均年収は430万円から530万円です。詳細は宅建士の年収解説記事をぜひ参考にしてみてください。
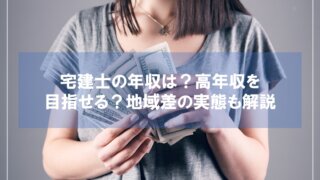
管理業務主任者も取るべき?
宅建に加えて管理業務主任者の資格も取るべきでしょうか? 就職という観点で言えば答えはNOです。持っていると良いこともあると思いますが、それほど必要性が高いとは言えません。
確かに宅建と管理業務主任者のダブルライセンスは立派です。でもその2つの資格をとって就職しやすくなるのはマンション管理会社に限られます。
就職先として不動産業界を幅広く検討している場合や不動産業界以外も含めて検討している場合はひとまず宅建だけに絞りましょう。宅建のほうが管理業務主任者よりもずっと知名度が高いので評価に結びつきやすいからです。
(不動産業界以外だと管理業務主任者という資格を知らない人のほうが多いです。「管理職向けの資格」だと誤解されることもあります。)
なおマンション管理会社限定で求職したい人は宅建は脇に置き、まずは管理業務主任者を、余裕がある場合はマンション管理士を合わせてとってダブルライセンスを狙うほうが良いと思います。
地域限定の良質な求人を自分で探したい
地域限定の良質な求人を自分のペースで探したい人は宅建Jobエージェントの姉妹サービス「不動産ジョブ」を活用しましょう。
不動産ジョブは不動産業界専門の求人情報検索サイトです。全国47都道府県の不動産関連求人が幅広く掲載されていて、納得いくまで時間をかけて求人を探せます。
勤務地や雇用形態を指定して検索できるのはもちろん「賃貸営業」「売買営業」「事務」といった職種や「業界未経験歓迎」「歩合・インセンティブ充実」などのこだわり条件も指定可能。自分に合った不動産業界求人を見つけやすいです。
無料で使えますので、まずは一度検索してみてください。
⇒ 不動産ジョブ
この記事のまとめ

今回は宅建取得後の就職についてお伝えしてきました。この記事の要点を復習すると次の通りです。
- 宅建資格を持っていると就職に有利である。その理由は「宅建業では5人に1人は必ず必要だから」「一定の法律知識を有することの証明になるから」「頑張れる人だとわかるから」である
- 宅建資格を取得することで一般の求職者だけでなく主婦や未経験者、高卒者・中卒者も就職しやすくなる
- 年齢との関係で言うと20代~30代は特に宅建資格の効果が大きい。40代~50代は主に不動産関連業において宅建が有利に働く。60代以降は軽めの求人において宅建が有力な武器になる
就職・転職に強い宅建資格をとり、競争に勝てる人材になりましょう。
以上、参考になれば嬉しいです。



