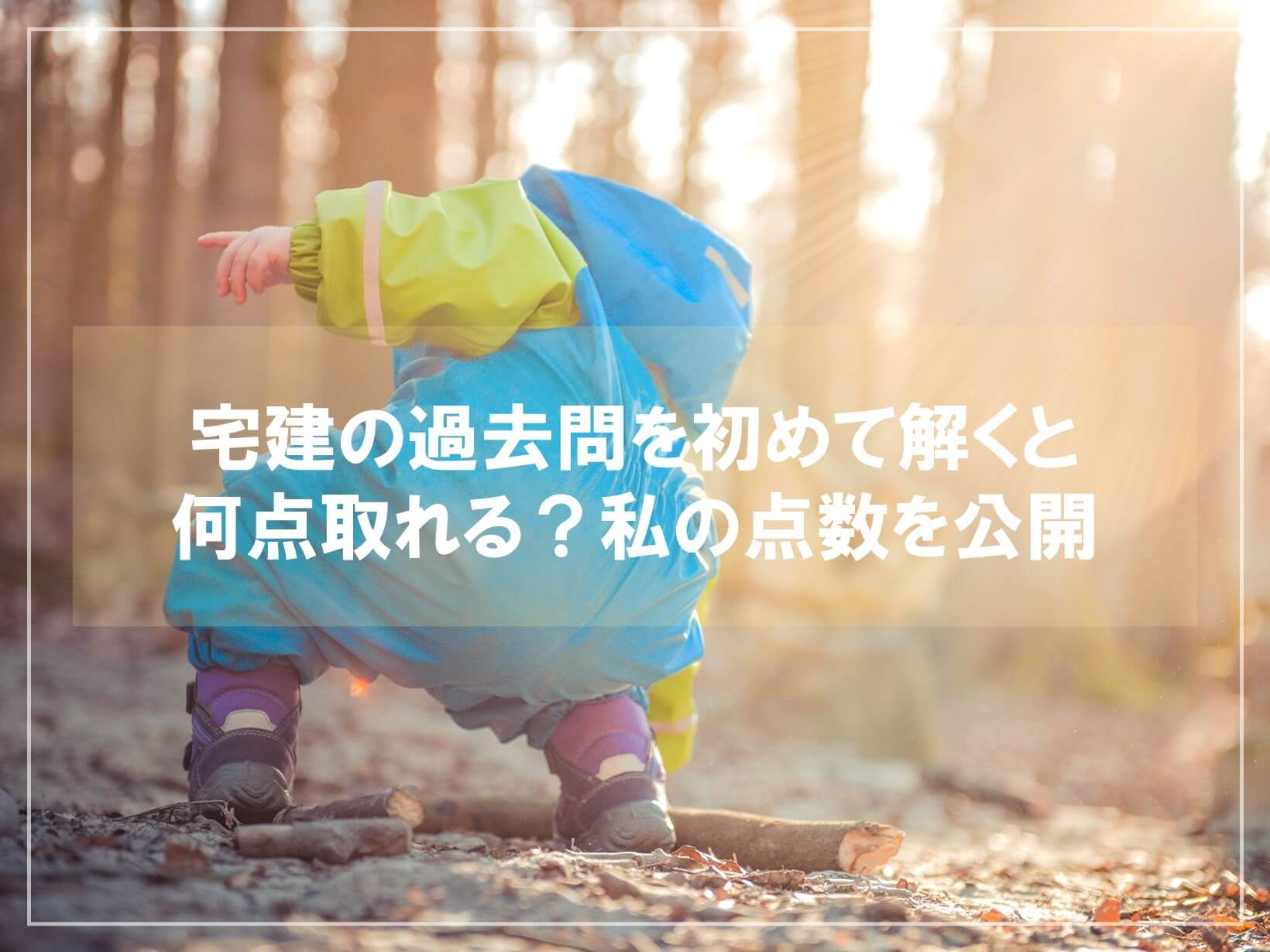宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。
今回は宅建の過去問を初めて解くと何点くらい取れるものなのか?という疑問に答えます。というのも私が宅建の受験対策をしているとき思い悩んだ疑問のひとつがこれだったんです。
なぜ思い悩んだのかといえば、自分が期待していたよりも得点できなかったから。そこで私と同じように「最初は何点くらいとれたらいい?」「こんな点数で受かるのかな?」と悩んでいる方に向けて私が受験当時に記録していたデータをお見せしたいと思います。
具体的には「○年度の過去問は初見で何点取れた」「次の年度の過去問は初見で○点取れた」というデータです。参考にしてみてください。
私が宅建の過去問を初めて解いて取れた点数
私が過去問10年分を初めて解いたときのデータを提示していきます。せっかくなので年度ごとの合格ラインを併記し、合格ラインとの差についても分析します。
※私は平成25年度試験の受験者だったため、お見せできるのは「平成15年度~平成24年度」の記録です。
1周目(初見)の得点
以下、宅建試験の過去問10年分解いたときの1周目のデータです(50点満点)。
| 年度 | 私の得点 | 合格ライン | 得点と合格ラインの差 |
|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 40 | 35 | 5 |
| 平成16年度 | 40 | 32 | 8 |
| 平成17年度 | 38 | 33 | 5 |
| 平成18年度 | 36 | 34 | 2 |
| 平成19年度 | 38 | 35 | 3 |
| 平成20年度 | 36 | 33 | 3 |
| 平成21年度 | 32 | 33 | -1 |
| 平成22年度 | 39 | 36 | 3 |
| 平成23年度 | 37 | 36 | 1 |
| 平成24年度 | 33 | 33 | 0 |
「私の得点」「合格ライン」「得点と合格ラインの差」の意味合いは次の通りです。
- 私の得点
- 過去問を解いて取れた点数
- 合格ライン
- その年度の合格基準点
- 得点と合格ラインの差
- 「私の得点」から「合格ライン」を引いた値。ゼロ以上ならその年度は合格(値が大きいほど良い成績)
10年分解いてみて、当時の私が思ったことは次のようなことでした。
- 40点台を目指してテキスト学習をしたつもりだが、結果はギリギリ40点をとれたのが2年分だけ。もっと得点できると思っていたのに。やはり宅建は一筋縄ではいかない
- とはいえ10年分のうち合格ラインを下回ったのは1年だけだった。思っていたよりも合格の可能性は高いかも
- しかし「得点と合格ラインの差」が1とか0の年もある。これでは試験本番で自分の合否は運に左右されてしまう。現状を脱して確実に合格できる実力を身に付ける必要がある
- 古い年度では「得点と合格ラインの差」が大きく、新しい年度では小さくなっている。宅建の難化傾向の表れかもしれない
参考までにお伝えすると、私は過去問10年分を解き始める前に膨大な時間をテキストの読み込みと理解に費やしました。そのためテキスト学習にそれほど時間をかけていない人と比べると、いくぶん良い点数になっている可能性があります。
2周目の得点
2周目の記録も残っていました。せっかくなので公開します。
| 年度 | 私の得点 | 合格ライン | 得点と合格ラインの差 |
|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 45 | 35 | 10 |
| 平成16年度 | 42 | 32 | 10 |
| 平成17年度 | 46 | 33 | 13 |
| 平成18年度 | 43 | 34 | 9 |
| 平成19年度 | 44 | 35 | 9 |
| 平成20年度 | 41 | 33 | 8 |
| 平成21年度 | 44 | 33 | 11 |
| 平成22年度 | 47 | 36 | 11 |
| 平成23年度 | 39 | 36 | 3 |
| 平成24年度 | 45 | 33 | 12 |
2周目ということで全ての年度で合格点以上をとれました。「得点と合格ラインの差」も拡大しているのが分かります。
しかし、同じ問題をすでに一度解いているはずなのに40点台前半に終わっている年度が散見されます。当時の私はこの結果に満足できず、もう1周解くことにしました。
3周目の得点
3周目の記録も残っていたので公開します。
| 年度 | 私の得点 | 合格ライン | 得点と合格ラインの差 |
|---|---|---|---|
| 平成15年度 | - | 35 | - |
| 平成16年度 | - | 32 | - |
| 平成17年度 | - | 33 | - |
| 平成18年度 | 48 | 34 | 14 |
| 平成19年度 | 47 | 35 | 12 |
| 平成20年度 | 47 | 33 | 14 |
| 平成21年度 | 47 | 33 | 14 |
| 平成22年度 | 48 | 36 | 12 |
| 平成23年度 | 48 | 36 | 12 |
| 平成24年度 | 48 | 33 | 15 |
どういう事情だったか正確なところは忘れましたが、平成15~18年は3周目をサボったようです…。サボった年度を除くと全年度で満点に近い点数が取れており、かなり良い結果です。
最初は解けないのが当たり前
私が過去問を初めて解いて得た結論は宅建の過去問は自分が期待するほどは解けないというものです。テキストを丹念に読み込んで十分過ぎるくらい知識をインプットしたと思っていても、いざアウトプットしようすると意外なほど良い成績が出ません。
その事実を目の当たりにして当時の私はかなりショックを受けたのですが、今考えてみればごく当然のことだと感じます。宅建試験は「問題を解く」試験なんです。だから「問題を解く」練習を繰り返し繰り返しトレーニングしないと点が取れるようにはなりません。
この結論をあなたへのアドバイスとして言い換えます。あなたが初めて過去問に取り組んだとき1周目の成績が思ったほど良くなかったとしても、あまり心配しなくて大丈夫です。
期待通りのスコアじゃなくても、2周、3周と繰り返せば自然に力はついていきます。過去問の反復練習を地道に積み重ねて、知識の定着と理解を図っていきましょう。
幸せに過去問を解く方法
私自身は独学をしていたので、自宅に引きこもって毎日机に向かって過去問を解いていました。毎日薄暗い部屋で過去問を解く作業は地道過ぎて辛いと感じることもありました。同じ行為の繰り返しなので精神に来てしまいます…。
でも近頃は通信講座のフォーサイト宅建士講座やスタディング宅建士講座を利用すればスマートフォンを使ってでいつでもどこでも気軽に過去問に取り組むことができます。
スマホがあればそれで良いので、カフェなど気が滅入らない場所でも勉強できますし学習時間の確保も簡単。ゲームアプリで遊んでいるような感覚で過去問に取り組めるので、明るい気持ちでサクサクと学習を進められます。
孤独の中、根性論で頑張るのはかえって効率が悪いです。少しでもハッピーな気持ちで過去問を解きたい人はフォーサイト宅建士講座やスタディング宅建士講座を使ってみると良いと思います。
私自身も実際に購入して試しました。どちらも自信を持ってオススメできる素晴らしい講座です。レビュー記事を書いて公開していますのでぜひそちらも参考に。


この記事のまとめ

今回は「宅建の過去問を初めて解くと何点くらい取れるものなのか?」という疑問に答えてきました。この記事の要点を復習しましょう。
- どんなにテキストを読み込んだとしても、初めて解いたときに取れる点数は良くて合格点前後
- 2周目、3周目と周回を重ねていけば得点は合格ラインを超えて伸びていく
- 宅建試験は「問題を解く」試験なので問題を解くトレーニングが不可欠
最初は皆、解けません。でも過去問演習を繰り返せば実力は必ず合格レベルに到達します。地道な努力を少しずつ積み重ねていきましょう。
以上、参考になれば嬉しいです。