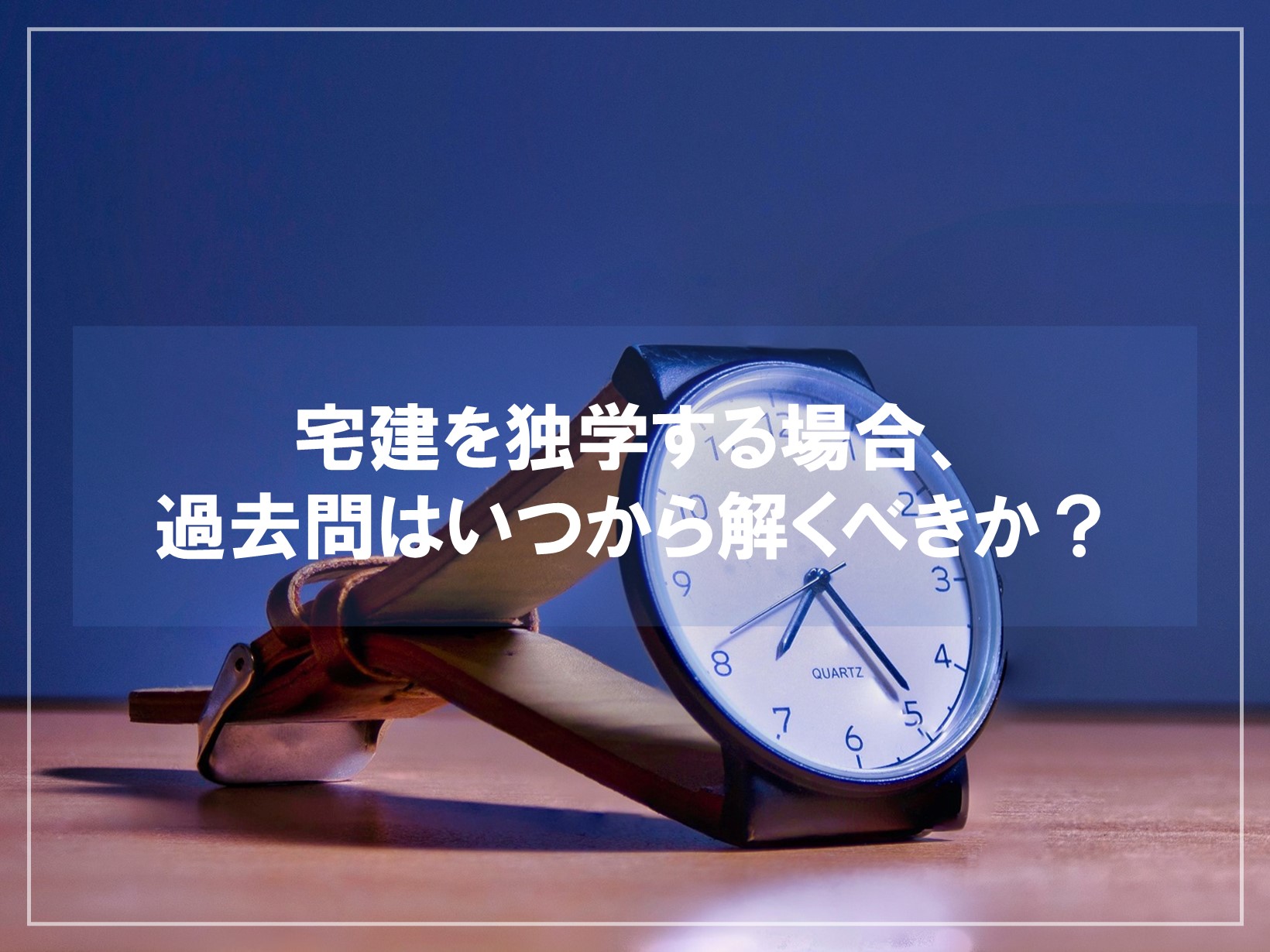宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。
今回は宅建を独学する場合、過去問はいつから解くべきか?という疑問に答えます。勉強の進め方で迷っている方がこの記事を読むと、今後やるべきことややるべきタイミングが考え方が明確になるはずです。ぜひ参考にしてみてください。
宅建を独学する場合、過去問はいつから解くべきか?
宅建を独学する場合、過去問はテキストを読み終わったら即解き始めるべきです。
つまり宅建試験の対策用のテキスト(基本書)を一読したらすぐにでも過去問に取り掛かるのがベスト。その理由を以下で説明します。
過去問演習は通過点に過ぎない
なぜテキストを読み終わったら即過去問を解き始めるべきなのかというと過去問演習は通過点に過ぎないからです。
どういうことか。私は宅建試験の独学勉強法をこのブログで繰り返しお伝えしていますが、その内容は次の3ステップとなっています。
- テキスト学習
- 過去問演習
- 予想問演習
この勉強法を見ていただくとわかるように過去問演習の後には予想問演習が控えているんです。したがって過去問演習は始まりでもなければ終わりでもなく、ただの通過点。
さっさと終わらせて次の段階に進まなければなりません。もたついていると、あっというまに試験日が来てしまいます。テキストを一読したら、ぜひその日のうちに過去問を解き始めましょう。
過去問演習は絶望的に時間がかかる
テキストを読み終わったら即過去問を解き始めるべき理由はもう1つあって、それは過去問演習は絶望的に時間がかかるからです。
これは体験してみるまでなかなかわからないかもしれませんが、はじめて過去問を解くときは本当に全然解けません。「あんなに頑張ってテキストを毎日読み込んだのに、ここまで解けないのか…。自分はどんだけバカなんだ」と思い知ります(私はそうでした)。
1問解くのに平気で5分、10分かかったりします。本来、宅建試験の問題は1問あたり2分で解かねばならないのに。
加えて、解き終わったら解説もしっかり読み込んでいく必要があります。そうしないと勉強になりません。なんだかんだで1問あたり15分くらい費やしても全然不思議ではないです。
でも1問あたり15分とすると試験1回分50問を解くのに12時間半かかる計算になります。文字通り日が暮れて1日が終わってしまいますよね。
* * *
といっても絶望的に時間がかかるのは最初のうちだけです。過去問2周目、3周目と回を重ねていくうちに解くスピードが速くなりますし、解説を読み込むスピードも上がります。「もうこの問題は解かなくてOK」と確信できた問題はスキップできます。
終盤は試験1回分50問の演習に3~4時間、あるいはもっと少ない時間で済むようになるでしょう。そこは安心してOKです。
ただ少なくとも最初のうちは思っていたよりも長い時間を使ってしまうことを覚悟しておきましょう。そのことに備えるためにも可能な限り早いタイミングで過去問演習をスタートするべきです。
練習問題を解く必要はないのか
「過去問を解く前に練習問題を解いたほうがいいんじゃない? 過去問にそんなに時間がかかるのは知識が定着していないってことだと思うから、一問一答集とかを使ってトレーニングしたほうが良い気がする」
そう思う人もいるかもしれません。でも私は独学する場合は一問一答集等の練習問題は不要だと思っています。つまり過去問と予想問(予想模試)以外の問題を解く必要はないです。
なぜか? シンプルに考えましょう。宅建試験は一問一答のような形式の試験ではありません。四肢択一式の試験です。四肢択一式の試験で多く得点して合格したいなら、四肢択一の試験問題を解くことが最も効果的なトレーニングになります。
陸上競技に例えるとわかりやすいかもしれません。長距離走に出ることになった人が「とりあえず短距離走の練習からやってみるわ!」と言い始めたら「何言ってんだコイツ??」って誰もが思うはず。
それと同じで宅建試験で勝ち抜きたければ宅建試験にできるだけ近い形式の問題集を使って訓練を重ねるべきです。
* * *
なお「過去問にそんなに時間がかかるのは知識が定着していないってことだと思う」は一理あります。確かに知識が定着していないからこそ多くの時間を要してしまうわけです。
でも知識は使うことによって定着します。つまり過去問を解いていく中で知識を使いますよね。その際は忘れた知識も復習して何度も使います。そうすることで自然と知識が脳に定着していきます。
はじめのうちは「俺って本当にポンコツだな、テキストで読んだこと全部忘れている」って心の底から思うことになるでしょう。大丈夫。過去問を3周もする頃には忘れたくても忘れらないほど覚えていて、全く違う世界が見えているはずですから。
何月に始めるべきか知りたい人へ
「過去問をやればいいっていうのはわかったけど、何月からやればいいのかを知りたいよ。テキストが終わったら即、とかじゃなくてさ」
そう思われた方もいるでしょう。その意見はもっともですので気持ちはわかります。過去問演習を始めるタイミングが早すぎれば時間が余ってしまいますし、遅すぎると試験対策が終わらなくなりますよね。
ただ、それでも「○月から始めればOK」なんてアドバイスをすることはできません。
そもそも人の知能や処理スピードには個人差があり過ぎますので、過去問演習の開始時期について一般的なアドバイスをすることは不可能です。
かといって、あなたが自分なりに「過去問にはこのくらいの時間(日数)がかかるだろう、だから○月から始めればベスト」と想定したとしても、実際にはそれよりもずっと多くの時間(日数)がかかることでしょう。
もし自分の想定よりも多くの時間を過去問にとられてしまうと、予想問演習の時間を十分に確保できなくなり、合格する可能性がガクンと下がるという最悪の事態に陥ります。
以上のことから、テキストを読み終わったらすぐに過去問を解き始めるつもりで勉強していく以外、取れる道はないと私は考えます。
* * *
逆に「思ったよりも過去問演習がスムーズに進んで、予想問演習もその分早く終わって時間が余った」という結果になる場合もあるでしょう。それはそれで良いじゃないですか。
やるべきことを終えられずに試験日を迎えてしまう人も大勢いるんです。そんな中で時間が余ったと言える状況にいられることは、むしろ「勝ち組」に属している証拠です。
そして余った時間こそ一問一答などの「四肢択一式以外の、自分が取り組みたいと思っていた問題集」に使ったら良いと思います。試験本番まで知識をさらに充実・定着させて合格可能性を100%に近づけていきましょう。
この記事のまとめ

今回は「宅建を独学する場合、過去問はいつから解くべきか?」というテーマでお伝えしてきました。
要点を復習すると、私の答えは「テキスト学習が終わったら即」というものです。その理由として以下2点をお伝えしました。
- 過去問演習は通過点に過ぎないから(予想問演習が控えている)
- 過去問演習は絶望的に時間がかかるから
さらに今回のテーマに関連する2つの疑問に答えました。
- 練習問題(一問一答集)を解く必要はないのか
- その必要はない。四肢択一式の問題を解くのが最も効果的なので、過去問と予想問(予想模試)で十分
- 何月から始めたほうがいいか知りたい
- 一般的なアドバイスは不可能。何月からと想定するよりも「テキストを読み終わったら即」と考えておくのが良い
以上参考になれば嬉しいです。