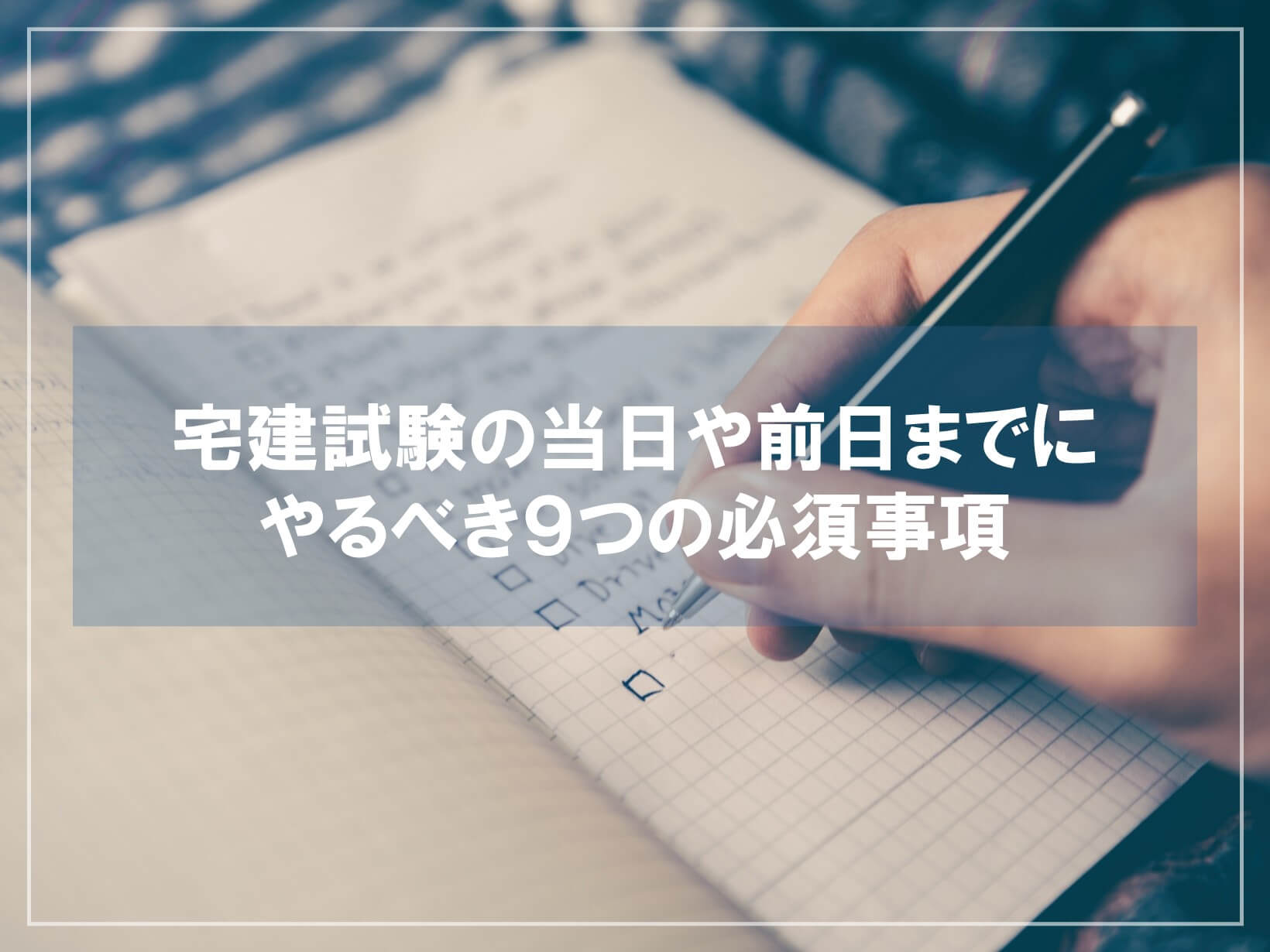宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。
本気で合格を目指している受験生ほど、試験日が近づくにつれて不安と緊張が高まるものです。それを和らげるためにその時その時で起こせるアクションがあります。
行動することでメンタルを適切にコントロールできれば、合格する可能性を一段と高められるはず。そこで今回は宅建試験の直前期にやるべき9つの必須事項についてお話しします。
- 受験日の前々日までにやるべきこと3つ
- 受験日の前日にやるべきこと3つ
- 受験当日にやるべきこと3つ
この記事を最後まで読んでいただければ、後悔しない受験につなげられるはずです。ぜひ参考にしてみてください。
前々日までにやるべきこと
宅建試験の前々日までにやるべきことは次の3つです。
- 試験会場まで行ってみる(下見)
- 試験問題を解く順番を決める
- 暗記をする
以下で順番に解説します。
試験会場まで行ってみる(下見)
受験日の前々日までにやるべきことの1つめは試験会場まで行ってみること(下見)です。
宅建試験の会場の多くは大学や公共施設です。普段は足を運ぶ機会があまりない場所であることも珍しくありません。なので試験のちょうど1週間前の日曜日に自宅から現地へ実際に移動してみるのがお勧めです。
そうすることで試験当日の交通手段が明確になりますし、当日の交通状況もなんとなく予想できるようになります。
到着までの過程で何かしら発見や気づきがあることも珍しくありません。「使えると思っていたバスの路線が、実は廃止になっていた」「駅の構造が以前とは変わっていた」等。
もしこういったことが試験当日に判明すると対処するのが大変ですが、事前にわかれば解決方法はいくらでもあります。
* * *
現地に着いたら、さすがに建物内に入ることはできないと思いますが、少しでも周囲の様子を確認しておくと良いでしょう。
意外と敷地や建物の入り口が分かりにくいかもしれません。「別の建物を目的の建物だと勘違いしてしまった」ということも起こりうるので、間違いないかどうか慎重に確認しておきましょう。
付近にコンビニはあるでしょうか? もしあれば当日急に筆記用具その他が必要になったとき購入できるかもしれません。チェックしておいてください。
以上のように事前に会場付近を訪れることで得られる情報は多いです。
試験問題を解く順番を決める
受験日の前々日までにやるべきことの2つめは試験問題を解く順番を決めることです。
宅建試験は第1問から第50問まで出題され、科目ごとに次の順となることが定番化しています。
- 最初の14問(第1問~第14問)
- 「権利関係(民法)」の問題
- 次の8問(第15問~第22問)
- 「法令上の制限」の問題
- 次の3問(第23問~第25問)
- 「税・その他」のうち税・鑑定評価の問題
- 次の20問(第26問~第45問)
- 「宅建業法」の問題
- 最後の5問(第46問~第50問)
- 「税・その他」のうち5問免除対象の問題
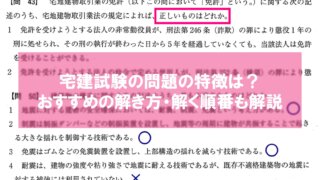
第1問から順序良く解くというのもありですが、あなたはどうしますか? まだ解く順番を決めていなかったら早めに決めて、自分が決めた順番で予想模試などを解いておくと良いでしょう。
もし試験本番がスタートしてから「何番から解こうかな?」なんて迷いにとらわれると、それだけで時間をロスしてしまいます。問題を解く順序をあらかじめ決めておけば問題を解く作業に全力を注げます。
暗記をする
受験日の前々日までにやるべきことの3つめは暗記をすることです。
私は宅建試験の学習では暗記ではなく理解を重視するべきだと考えています。理解した上で過去問や予想問題を繰り返し解いていれば、無理に暗記しなくても知識は自然と頭に定着するからです。
しかしこの方法も完璧ではなく、記憶に残りにくい用語や数字というのもある程度は出てくるものです。そこで理解重視の学習を目一杯やった後の最終手段として暗記に頼ります。
暗記の方法はひとそれぞれ好きな方法をとればいいと思いますが、手軽でおすすめなのは暗記カードを作ることです。
こういった商品を買って、おもて面に簡単なクイズを書き、うら面に暗記したい用語を書きます。自分専用の暗記カードを作るだけでもある程度頭に知識が残ります。
暗記カードが完成したらカードを使って脳に知識を刻み付けていきましょう。
* * *
このような「暗記のためだけの作業」は試験の1週間前から前々日くらいまでの間にやれば十分です。逆に言えばその時期までは繰り返し問題を解き続けて「知識が自然に記憶されていく」ことを優先してください。
直前期の暗記は少々しんどい作業になりますが、宅建試験から解放されるまでもう少し。乗り切りましょう。
前日にやるべきこと
宅建試験の前日にやるべきことは次の3つです。
- 持ち物の最終確認
- 最後の模擬試験演習
- 早めに寝る
以下で順番に解説します。
持ち物の最終確認
受験日の前日にやるべきことの1つめは持ち物の最終確認です。
会場に持って行くものを確認しましょう。試験当日の受験案内でも指定されていると思います。次のような内容です。
- 受験票
- マスク
- BかHBの黒鉛筆又はシャープペンシル
- プラスチック製の消しゴム
- 腕時計
⇒ 【RETIO】インターネットによる宅地建物取引士資格試験案内
人により、あるいは状況により、次のものも用意します。
- 傘などの雨具
- 現金の入った財布(移動や食事に使う場合)
- ハンカチ
- ティッシュ
- メガネ
- 薬
- 参考書(テキストや問題集)
- まとめノート
必要な持ち物は一度紙に書き出して持ち物リストを作っておくのがおすすめです。翌日、出発前の最終確認の時も使えます。
最後の模擬試験演習
受験日の前日にやるべきことの2つめは最後の模擬試験演習です。
予想模試1回分を「試験本番と同じ時間帯に」「制限時間2時間で」解いてください。まだ1度も解いていない模試が手元にあるなら、それを解くのが理想的です。
本試験のリハーサルを自主的に行って神経回路を最適化しておけば、当日は脳の反応が早くなり、ムダに緊張することも無くなり、パフォーマンスが向上するはずです。
試験前日の模擬試験演習だからこそ「これが本番だ!」と気合を入れて、100%フルパワーを出し切りましょう。そうすればあなたは自分の能力を120%にまで高めて本試験に臨めます。
早めに寝る
受験日の前日にやるべきことの3つめは早めに寝ることです。
早めに寝る準備として、夜の食事はあっさりしたものを軽めに取るようにしてください。下手にゲンを担いでカツ丼を食べたりして、翌日胃もたれをしたりお腹が痛くなったりしたらイヤですよね。
伝統的な日本食のような、消化器官にやさしいものを食べるのがおすすめです。
天気予報もチェックしておきましょう。明日は晴れるのか? 雨なのか? 天気次第で持ち物も若干変わってきますので、確認を忘れずに。
食事と天気予報の確認が終わったらいつもより早くベッドで横になりましょう。ベストな成果を出すためには何よりも睡眠が重要です。
もしかすると緊張してなかなか寝付けないかもしれません。目を閉じて気分を落ち着けるだけでも脳はリラックスします。これまでの自分の頑張りを自分でねぎらいつつ、明日のために頭と体を休めてください。
当日にやるべきこと
受験日の当日にやるべきことは次の3つです。
- 早めに出発する
- 統計・法改正の資料をもらう
- トイレの場所確認
以下でもう少し解説します。
早めに出発する
受験日の当日にやるべきことの1つめは早めに出発することです。
時間の余裕は心の余裕に直結します。当日は早めに身支度を済ませて、予定より少し早くてもいいので自宅から出てしまいましょう。家で落ち着かずソワソワしているよりも、外に出て新鮮な空気を吸って景色でも眺めたほうが気持ちが落ち着きます。
なお当日は事故による通行止めや渋滞、電車の遅延といった不測の事態が起こらないとも限りません。でも時間の余裕さえあれば、いざというときはタクシーを捕まえて会場へ急いでもらうという手段がとれます。
早め早めに行動していきましょう。
統計・法改正の資料をもらう
受験日の当日にやるべきことの2つめは統計・法改正の資料をもらうことです。
当日の試験会場の周辺では資格対策予備校のスタッフの方が受験生の到着を待っています。何のためかというと…営業のためです!
言葉を選ばずに言うと今年の試験に落ちるであろう人を囲い込むために活動されています。以下は私(杉山貴隆)の経験談ですが、会場まであと数十メートルというところでとても綺麗な女性に声をかけられました。

すみませ~ん、宅建受ける方ですか?

? はい、そうですが

私○○資格学校の者なんですけど、これ、どうぞ!
試験直前の確認ポイントがつまった冊子です!(ニコッ)

あ、ありがとうございます。
あ~これいいですね。助かります

いえいえ~!!
ちなみに…合格する自信とかって、どんな感じなんですか?

うーん、わからないですが、多分大丈夫かなと思いますが

あはっ!そうなんですね!
スゴいですね! 頑張ってくださぁい!

はい(//▽//)

ところで、いまウチで宅建の受験生の皆様にアンケートをとってまして、よかったらこちらにお名前と住所を書いてもらえたら

!?

お名前と住所書いてもらえたら、解答速報とかお送りできるんですけどぉ…

あ、スミマセン、急いでいるんで大丈夫です!
(スタスタスタ)
…ということで、試験会場の周辺に綺麗な女の人がいたら注意! 私のように普段女性に相手にされていない男性は声をかけられただけで嬉しくなって、つい話し込んでしまいます。
宅建試験は男性の受験生が多いので意図的に美女を配置しているんでしょうね。そしてそれにまんまとひっかかる私…。
営業さんの相手はほどほどにして、さっさと会場に着いて着席し、深呼吸でもしたほうが有益です。先を急ぎましょう。
ただこういった予備校スタッフの方たちは声をかけると同時にその年の統計や法改正の要点をまとめた資料を渡してくれることが多いので、受け取っておくようにしましょう。試験開始の直前の復習に役立ちます。
トイレの場所確認
受験日の当日にやるべきことの3つめはトイレの場所確認です。
いよいよ会場に到着したら、掲示されている案内を参照しつつ自分が試験を受ける部屋(教室)および席を探します。わかりにくいと思うので、もしわからなければ会場運営スタッフの方にたずねてみましょう。
自分の席の場所がわかったら、最寄りのトイレを探して用を済ませておきます。トイレの場所さえ分かっていれば他に気を取られることも無いでしょう。
トイレ関係で気を付けてほしいのは当日の飲み物です。コーヒーやお茶は控えることを強く推奨します。これらの飲み物には利尿作用がありますので、飲んでしまうとあなたは確実にいつもより多くトイレに行きたくなります。
私は宅建試験のときはコーヒー・お茶はとらなかったので大丈夫だったのですが、その2年後に受けた管理業務主任者試験で失敗しました。
試験会場に向けてバスで移動しているときから缶コーヒーを飲んでいたんです。そうしたら試験開始までに3回トイレに行き、試験中も膀胱が不穏な感じでした。
幸い漏らすことはありませんでしたが、集中力をかなり削がれました。以上の経験から当日の飲み物は水にしておくことをオススメします。
トイレが済んだ後はどうしたら良いでしょうか? 試験開始時刻までテキストや問題集、先に受け取った要点資料を見ながら、自分なりに最終チェックをする人が多いと思います。
しかし私自身は受験当時は逆のことをしました。テキストも問題集も一応持ってはいましたが、全く開きませんでした。むしろ目を閉じて精神を統一することに多くの時間を使いました。
なぜ周囲の人のように最後まで参考書を読まなかったのかというと、試験会場に着いてからのたかだか小一時間の勉強で合格・不合格が変わるとは到底思えなかったからです。
私は宅建試験に確実に合格することを目指して前日まで必死になって勉強していました。なので試験を受ける直前の段階で「もう結果は出ている」と考えていました。
試験直前に焦って知識を詰め込むのではなく、目をつむってこう自分を励ましました。「今日はベストを尽くすのみ。そうすれば絶対に合格する」。心の状態を保つことにだけ気を配ったんです。
それでも試験開始直後はかなり緊張しましたが、問題を解いているうちに少しずつリラックスしていきました。なんとか1時間30分程度で全ての問題を解き終え、軽く見直しをしたり、飛ばした問題を解いたりもできました。
結果は50点満点中40点を取り合格です。「試験会場に着いてからの勉強で合否は変わらない」。この考え方は真理だと実は今でも思っています。
あなたも試験会場に到着したその時「合格できる自分」になっていてください。未来の自己像をイメージしつつ、全身全霊をかけて学習しましょう。
この記事のまとめ

今回は宅建試験の当日や前日までにやるべき9つの必須事項をお伝えしました。この記事の要点を復習すると次の通りです。
- 宅建試験の前々日までにするべきこと
- 会場の下見
問題を解く順番の決定
どうしても頭に残らなかった数字や用語の暗記 - 宅建試験の前日にするべきこと
- 持ち物の最終確認
最後の模擬試験演習
早めに寝る - 宅建試験の当日にするべきこと
- 早めに出発する
統計・法改正の資料をもらう
トイレの場所確認
ところで、試験終了後の夕方から夜にかけては何をしましょうか? もちろん美味しいものを食べたりお酒を飲んだり、それまでガマンしていた色々なことをパーッとやりたいですよね。
そんな中で1つ忘れてないで欲しいのは解答速報を見ることです。試験当日の夜にかけて大手資格対策予備校が宅建試験の模範解答をウェブ上で公開します。
試験中、問題用紙に自分の解答をメモしておけば、それを持ち帰って解答速報と照らし合わせて自己採点をすることも可能です。
私自身、受験した日の夜は「解答速報で自分の点数を見極めつつ、SNSで他の受験生の喜びの声・悲しみの声を眺める」という過ごし方をしました。
解答速報サイトのまとめ記事を用意していますので、試験後に利用していただければと思います。

以上、参考になれば嬉しいです。