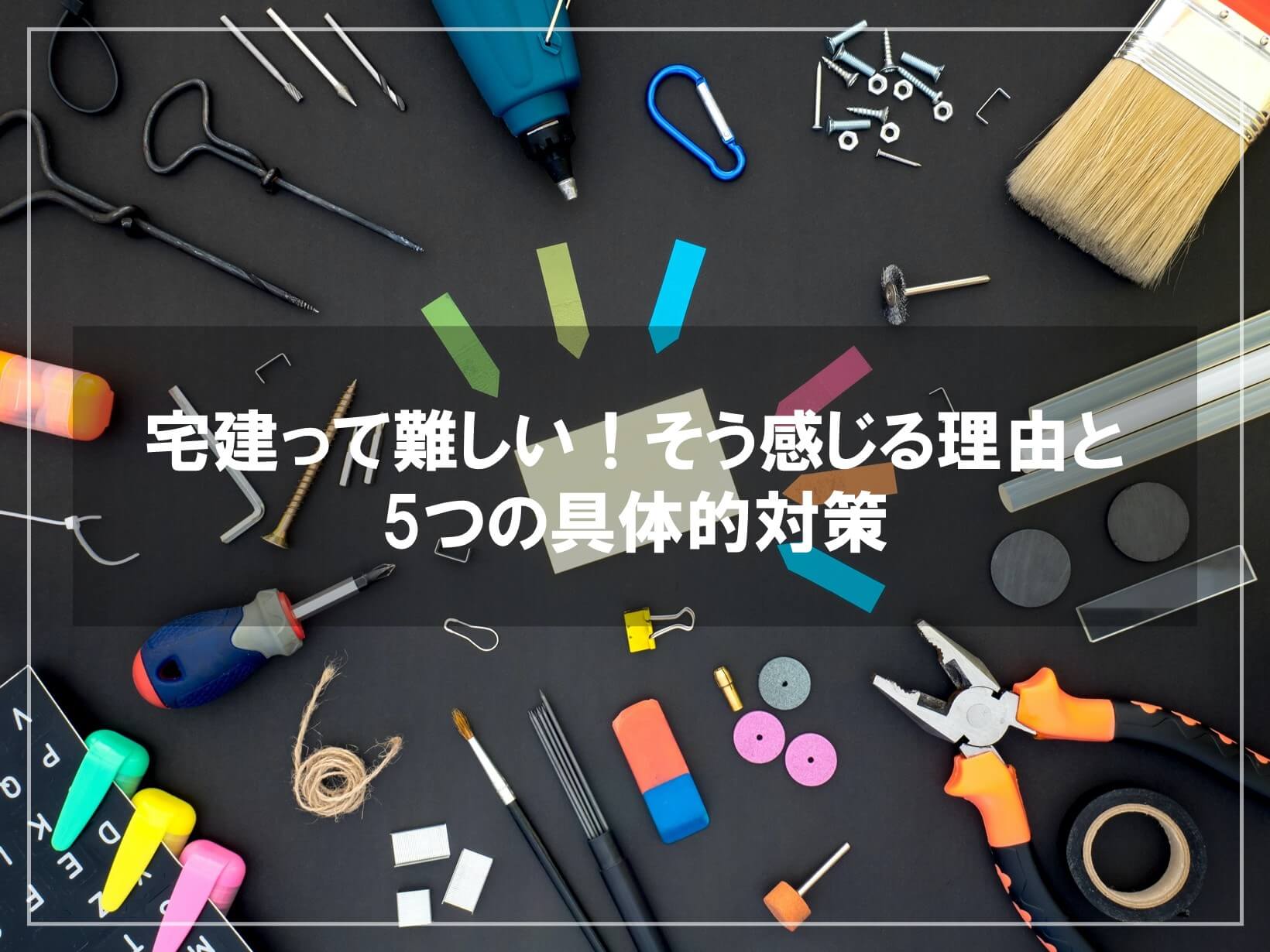宅建試験に一発合格した宅建士杉山貴隆です。
宅建試験の勉強を始めてみると「意外と難しい!」「簡単って聞いていたのに話が違う…」「どうしたらいいの?」そう感じている人もいるのではないでしょうか。使われている言葉も概念も、何もかもが難しく感じられますよね。
そこで今回は宅建試験が難しい理由を分析し、難しさを乗り越えるための具体的対策を紹介します。一読していただけるとこれまでとは少し違う捉え方ができるようになり、受験勉強がスムーズに進むようになるはずです。ぜひ最後まで読んでみてください。
なぜ宅建の資格試験は難しいのか
宅建試験が難しい理由をひとことで言うと落とすための試験だからです。宅建試験は毎年約20万人もの大量の受験者がいるのですが、その8割以上を不合格にするために意図的に難しく作ってあります。
だからもしあなたが「宅建試験って難しい」と感じたとしても、不安になる必要はありません。もともと落とすための試験として作られていますので、受験生はみんな難しいと感じています。難しく作られたものを難しいと感じるのはごく自然なことです。
とはいえ単に難しいと感じているだけでは合格には近づけません。難しいと感じる試験に対してどう対策すれば良いかを検討していきましょう。
私のおすすめの方法はあなたが具体的に何をどう難しいと感じているのか一度冷静になって考えてみることです。宅建業法や権利関係など特定の科目が難しいのでしょうか?
あるいは過去問を解いてみたら難しいと感じた? もしかすると模擬試験を受けてみたら思っていたよりずっと難しかったということかもしれませんね。
いずれにしても自分が宅建のどういう側面を難しいと感じているのかを見極めましょう。そしてその内容に応じた対策を打っていくことで問題は解決するはずです。
宅建試験が難しいと感じるときの対策5つ
ここでは宅建試験の難しさを感じるポイントごとに必要な対策を紹介します。
宅建業法が難しい場合の対策
宅建業法には「こんな決まりがあるの!?」と驚いてしまうような規定・制度がたくさん定められていますよね。業法が難しいと感じる場合は「宅建業者は悪だ」「消費者は善だ」という観点でもう1度学習してみてください。
宅建業法は極端な言い方をするなら「不動産屋が無知な消費者をだまして不当な利益を得ないようにするための法律」です。具体例を挙げると、不動産屋に悪いことをさせないために宅建業法で免許制度が定められ運用されています。
また不動産屋に法律を守らせるために従業員5人に1人の割合で宅建士を雇う義務が定められています。さらに売主が宅建業者のときには特に厳しくするため8種制限が設けられていたりもします。
なぜこんなに複雑で奇妙な制度があるんだろう?と思ったときは宅建業者から消費者を守るという目線でとらえ直してみましょう。ナルホド!と腹落ちするはずです。
宅建業法科目の問題を解くときのテクニックについては宅建業法科目の範囲・問題例・解答のコツの記事も参考になると思います。
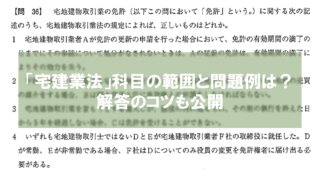
権利関係が難しい場合の対策
権利関係は宅建試験の中でも最も難しいと言われている科目です。権利関係が難しいと感じる場合は「民法は対立する二者の利害のバランスをとるための法律である」「バランスのとり方には根拠がある」という観点でもう1度学習してみてください。
たとえばAがBの詐欺や強迫により自己所有の土地をBに売り、Bがその土地を善意のCに売った場合。「AがAB間の土地の売却を取り消せるか」という論点がありますよね。
Bの行為が詐欺だろうと強迫だろうと、本来はAもCも悪くありません。Aは詐欺または強迫の被害にあっただけですし、Cは何も知らずに買っただけですから。
でも土地は1つしかないので、AのものになるかCのものになるか、どちらかしかありません。つまりAとCは利害が対立しているのですが、こういうとき土地がどちらのものになるかが法律で決まっていないと喧嘩になってしまいます。
そこで民法は「Bの行為が詐欺のときは、AB間の売買の取消は不可。土地はCのもの」「Bの行為が強迫のときは、AB間の売買は取消可。取り消した場合、土地はAのもの」と決めています。そうすることでAとCの利害のバランスを取っているんです。
* * *
でもなぜ「Bの行為が詐欺のときは土地はCのもの」で「Bの行為が強迫のときは土地はAのもの」と決めたのでしょうか。逆ではダメなのでしょうか。実は詐欺のときCが有利になり強迫のときAが有利になることには根拠があります。
- Bの行為が詐欺のときは、Aはよくよく注意をしていれば騙されることを防げたかもしれないから、Aの落ち度はゼロではない。ゆえにAよりもCを保護するべきなので、AB間の売買の取消は認めない
- Bの行為が強迫のときは、Aの落ち度はゼロ。この場合Aは全く悪くない。強迫によってなされたAB間の売買をAの意志に反して有効とすれば、正義に反する。だからAが取り消したいという場合には取消可とする
こんな感じでAの責任の度合いに応じた結論となっています。何の根拠もないバランスのとり方をしているのではなく、それなりの理由・理屈があるんです。
民法や権利関係で扱われるその他の法律は「対立する二者の利害のバランスをとる」という原点に立ち返って考えるとスッと理解できるようになります。
また「そのようなバランスのとり方にした理由や根拠」の部分もおさえておくと、未知の論点を扱った出題に対しても推論を働かせて答えることが可能になります。
権利関係科目の問題を解くときのテクニックについては権利関係科目の範囲・問題例・解答のコツの記事も参考になると思います。
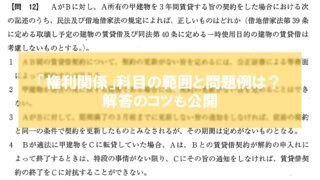
法令上の制限が難しい場合の対策
法令上の制限が難しい場合は暗記しないことを意識してください。
法令上の制限の難しさの原因は覚えておかなければならない数字や用語の多さです。やれ1,000㎡だ5,000㎡だ、やれ第一種中高層住居専用地域だ高度地区だ高度利用地区だと、もうわけがわからなくなりますよね。
こういったものは一度に全部暗記しようと思っても無理です。かといって何回かに分けて暗記してもすぐ忘れてしまいます。だから暗記してはいけません。暗記は諦めましょう! 私は早々に諦めましたよ。
ではどうすればいいかというと問題を繰り返し解いていく中で自然と脳に定着することを狙うのが良いです。最初はテキストを見ながら過去問を解きます。1~2回解いてみて「何となくわかったかな」という気になったら次はテキストを見ないで解きましょう。
解き終わったら、正解した問も不正解だった問も解説を読み込んで復習です。あとはこれを繰り返します。4回、5回と解けばイヤでも自然に覚えてしまいます。
なお1日のうちに何度も解くのではなく、今日解いたら次は明日、その次は明後日、という具合に少し時間をあけて解くのがコツです。
1日とか数日という単位で時間を空けて何度か繰り返すと記憶が強化されて非常に忘れにくくなります。このことは、エビングハウスという心理学者の研究によって科学的に実証されています(エビングハウスの忘却曲線)。
ひたすら数字や用語を暗記しようと一生懸命になるのではなく、過去問等の問題を何度も解いていつのまにか覚えている状態を目指してください。
法令制限科目の問題を解くときのテクニックについては法令制限科目の範囲・問題例・解答のコツの記事も参考になると思います。
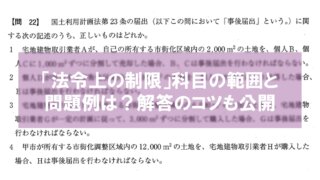
過去問が難しい場合の対策
過去問を解いていて難しいと感じることがあると思いますが、とるべき対策はありません。あまり気にしないで大丈夫です。そもそも宅建の過去問はテキストを1~2回読んだくらいで解けるものではないので。
たとえば私の場合テキストを深く読み込み、サブノートも大量に作ったのに、過去問10年分を最初に1周したときは50点満点中30点台前半くらいしかとれず、かなり焦りました(過去問を初めて解くと何点取れるの記事を参照)。
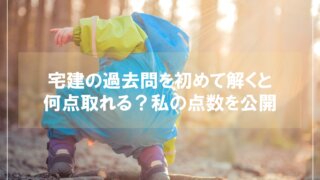
でも今にならわかるのですが誰でも最初は解けないものなんです。なぜか? 問題を解く練習をまだ全然していないからです。短距離走を早く走る理論を学んだところで、実際に走る練習をしていなければ速く走れないのと同じです。
なので今の時点で解けないことは全く気にしなくて構いません。気持ちを切り替えて過去問演習を2周、3周と続けてください。そして1周するたびに解説をしっかり読み込んで理解してください。これを愚直に繰り返していれば難しいという感情は次第に薄れていきます。
なお過去問の難易度は年度によってばらばらで特に難しい年度もあります。たとえば2014年(平成26年)と2015年(平成27年)の宅建試験は難しく、受験生の得点も全体的にかなり低かったようです。
その次に難しかったのが2008年(平成20年)・2009年(平成21年)・2012年(平成24年)だと言われています。
これらの年の過去問を解いて難しいと感じた人は「特別に難しい年度だったんだ。なら解けなくても仕方ないや」と気楽に受け止めるようにしましょう。
模試が難しい場合の対策
LEC・TACなどが実施または出版している予想模試が難しいと感じた場合、その原因は2つ考えられます。原因の1つめは資格スクールの模擬試験は実際に難しく作っている場合が結構多いということです。
特に会場で受験するタイプの模試はかなり難しいという声がよく上がっています。なぜ難易度を上げた模試を作るのかというと、受験生に「難しい!このままではヤバい!」と思わせて、本試験までにできる限り多く勉強してもらおうという意図があるんです。
なのでこういった資格スクールの模試を難しいと感じた場合、深刻になることはありません。「故意に難しく作ったんだろうなぁ」と思っておけばOKです。
そして解いた模試が難しかろうとそうでなかろうと、その後にやるべきことは決まっています。淡々と模試の復習をして本試験に備えましょう。
* * *
資格スクールの予想模試を難しく感じる原因の2つめは初見の問題だからです。
模試を受ける人はたいてい過去問を何度も解いている人ですよね。過去問って繰り返し解いていると当然ですがサクサク解けるようになります。
その感覚のままいざ模擬試験を受けると「あれ?いつものようにサクサク解けない…」という感覚に陥ります。それで「難しい」と感じるわけです。
これもそういうものなので気にしないでください。過去問を繰り返し解いた人はみんな同じように感じていますから。
そして解いた模試が難しかろうとそうでなかろうと、やはりやるべきことは決まっています。淡々と模試の復習をして本試験に備えましょう。
よくある質問
宅建関連の難しさについてよくある質問に答えます。
5問免除のための登録講習は難しい?
5問免除を受けるために受講する登録講習は修了試験も含めて難しくないです。安心して受講を申し込みましょう。5問免除や登録講習の詳細は5点免除って何?の記事で解説しています。

用語が全体的に難しい…
宅建関連の用語は耳慣れないものが多く、確かに難しいと感じられます。こればかりは慣れるしかないというのが正直なところです。私も民法の担保権の用語(抵当権・先取特権・質権など)はたびたびわからなくなるので難しいと感じていました。
用語の意味がわからなくなったらその都度テキストや用語集で意味を調べましょう。そして意味がわかったら過去問を解いてください。知識を実践で使うと、より深く理解できますし脳に定着しやすくなります。テキストで調べる他に、ネット上の用語集を使うのもオススメです。
試験本番は難しい?
宅建試験の本番は少し難しく感じられます。初見の問題は難しく見えるものだからです。
おそらくあなたは本試験で「あっ、難しいな…最後まで解けるか不安だな…」と感じることでしょう。でも恐るるなかれ。周りの人全員が同じように感じていますので条件は同じです。
試験当日は今まで積み重ねてきた成果を発揮するつもりで全力を尽くせば大丈夫。結果はきっとついてきます。
今年の宅建は簡単?難しい?
「今年の宅建」が未来の宅建試験のことであれば、難しいかどうかは誰にもわかりません。とはいえ宅建試験は年々難化していますから、今年も難しいのだろうと予想して今のうちにできる限りの対策をとっておきましょう。
「今年の宅建」が既に終わった宅建試験のことであれば、資格スクールの講師の先生やスタッフが試験講評を出しますので、そちらを参照することで難しいかどうかわかると思います。試験講評は解答速報サイトまとめ記事からアクセスできます。

この記事のまとめ

今回は「宅建試験が難しい理由」と「難しさを乗り越えるための具体的対策」についてお伝えしました。この記事の要点を復習すると次の通りです。
- 宅建試験は落とすための試験であり、難しいと感じるのは自然である
- 自分が何を難しいと感じているのかを明確にして、その内容に応じた対策をとると良い
上記の指摘に基づき「科目ごとの対策」「過去問が難しい場合の対策」「模試が難しい場合の対策」について、それぞれ述べてきました。
- 宅建業法が難しい場合
- 「宅建業者は悪だ」「消費者は善だ」という観点でもう1度学習する
- 権利関係が難しい場合
- 「民法は対立する二者の利害のバランスをとるための法律である」「バランスのとり方には根拠がある」という観点でもう1度学習する
- 法令上の制限が難しい場合
- 暗記しないことを意識し、問題を繰り返し解いていく中で自然と脳に定着することを狙う
- 過去問が難しい場合
- 気にせず過去問演習を繰り返す
- 模試が難しい場合
- 気にせず模試を復習する
以上、参考になれば嬉しいです。
* * *
次回は宅建の試験時間と時間配分について考えていきましょう。下のブログカードをタップすると移動できます。