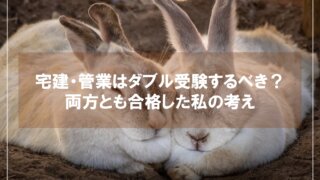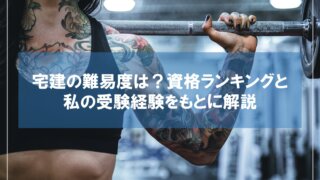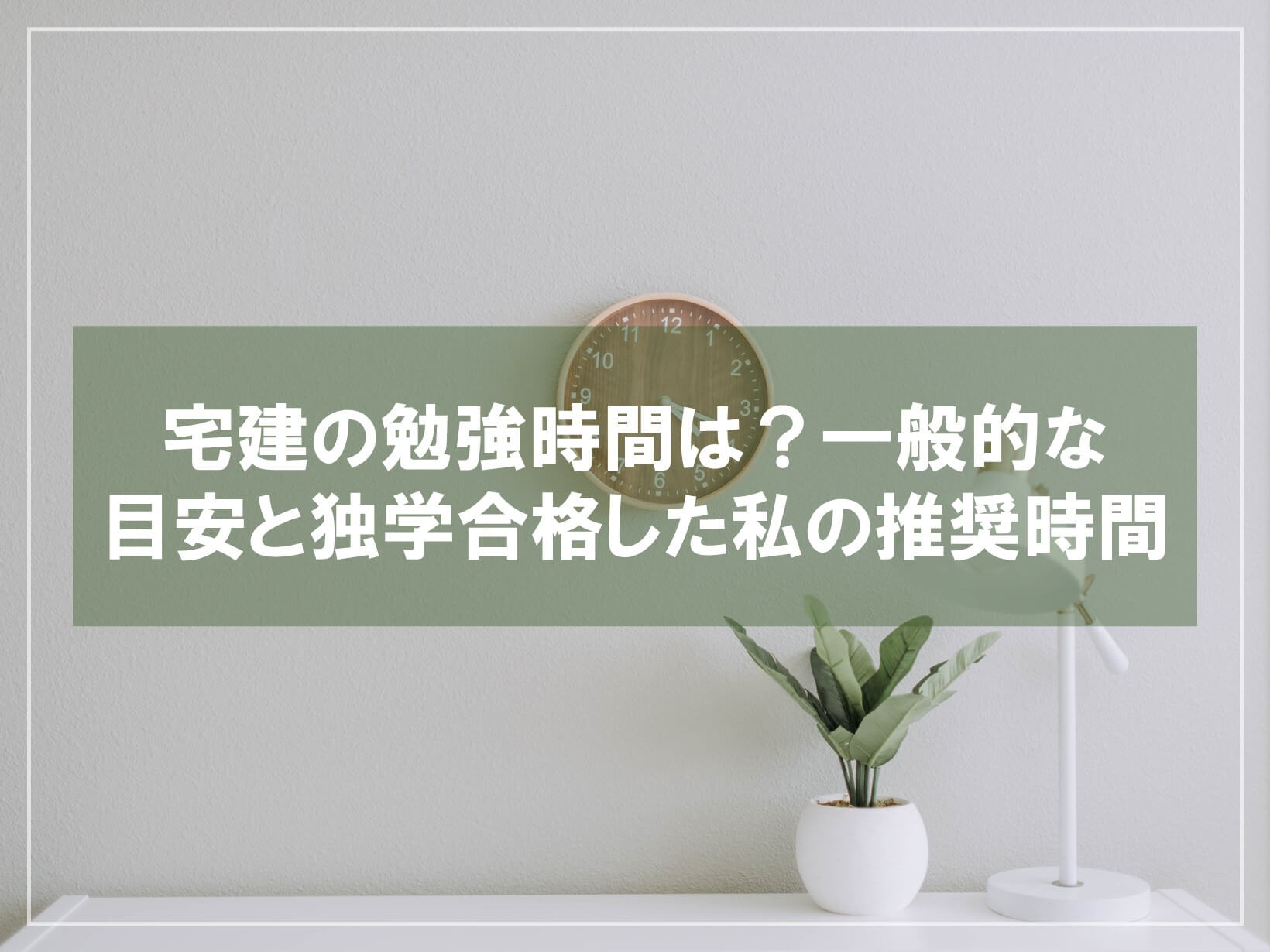宅建試験に一発合格した宅建士杉山貴隆です。
資格試験に受かりたければ勉強をする。これはどの資格でも同じです。ではどのくらいの時間勉強すればいいのでしょうか? 必要な学習時間は資格試験によって異なり、その資格固有の学習時間を把握して初めて計画的な学習が可能になります。
そこで今回は宅建試験の合格に必要な勉強時間の目安についてお伝えします。一般的な意見ばかりでなく私個人の考えにも触れていきます。
私自身は知識ゼロの完全な初心者の状態から勉強を始めて独学で宅建試験に合格しました。その経験に基づいて述べていきますので、私と同様に宅建のことを何も知らないところからスタートする人にとっては特に参考になると思います。
ぜひ最後まで読んでみてください。
宅建試験の合格に必要な勉強時間
まずは結論ですが、宅建試験の合格に必要な勉強時間の目安はおおよそ300時間だと言われています。これより多く言う人も少なく言う人もいますが、さまざまな見解を平均して300時間くらいだとするのが一般的です。
一方で私個人としては本気で合格したいのなら400時間勉強することを推奨しています。その理由は皆が300時間勉強する中で、自分の合否を運に左右されないためにはプラス100時間勉強するのが有効だからです。
以下でなぜ400時間勉強するのが良いのかをもう少し詳しく説明していきます。
宅建試験の合否決定プロセスとは
重要な前提として宅建試験で合格・不合格がどうやって決まるのかを知っておきましょう。すごく簡単に言うと成績上位の3~4万人程度が合格者になります。もう少し順を追って説明すると、宅建試験の合否決定プロセスは次の通りです。
- 試験実施団体が試験を実施した
- 受験生全員分の採点完了後、受験生約20万人の得点データを点数の良い順に並べた
- 上位3~4万人とそれ以外とを区切るラインは50点満点中35点であった
- そこで合格点を35点に決定
- その年は35点以上の人が合格、それ以外は不合格となる
合格できるのは上位15%
上記のようなプロセスで合格・不合格が決まりますので、合格したい受験生は何としても上位3~4万人の中の1人にならなければなりません。
宅建試験は毎年20万人程度が受験しますが、その中の上位3~4万人とは上位15%の水準です。宅建合格を目指す100人がいたら、そのうちわずか15人しか合格しない狭き門なんです。
合格するために必要なこと
では上位15%に入り込むために、あなたはどのような戦略をとればいいのでしょうか。
仮に「宅建試験の合格に必要な学習時間は300時間だ」という最も一般的な説に従って300時間勉強する戦略を採用したとします。しかし他の非常に多くの人も宅建試験の合格には300時間の学習が必要だと考えているので、同じくらい勉強して受験に臨みます。
するとどうなるかというとその年の合格点(たとえば35点)付近の点数を取る人が大量に出てきて、あなたもその1人になります。
運よく合格点プラス1~2点くらいの点数をとれれば良いのですが、運悪く合格点マイナス1~2点で着地してしまうと不合格という結果に終わってしまいます。
宅建試験に運なんて関係あるの?と思われるかもしれませんが、たとえば自分と相性の良い問題が本試験に出題されるかどうかは完全に運です。また試験当日の精神状態や体調といったことも少なからず運次第の面があります。
まとめると、他の多くの人と同様に300時間くらいしか勉強しないのであれば、試験の結果は最後まで運に左右されてしまうのです。
それで良いと思える人は構いません。でももし「運に左右されるなんてゴメンだ。自分の実力で絶対に合格したい」と考えるなら、もっと強力な戦略が必要になります。
採るべき戦略
そこで採用するべき戦略が私が最初にお伝えした「300時間に追加で100時間。合計で400時間勉強する」というものなんです。単純に他人よりも学習量を増やすことで合格点プラス5点くらいの得点を狙います。
合格点プラス5点もの点数をとる実力がつけば、当日運が悪く2点失ったとしても合格点プラス3点で着地できます。運が左右する不確定な部分を抑え込んで、確度の高い合格を目指せるのです。
私は以上の考えに基づいて400時間の学習を推奨しています。
もちろん学習時間を増やすだけ増やして、考えも無しにテキトーな勉強していたのでは合格は望めません。合格するためには勉強の量だけでなく、どのような順序でどんな勉強をするかといった質の部分も重要です。
私が採用した具体的な方法は宅建試験のおすすめ勉強法の記事で詳しく解説しています。

よくある質問
宅建試験の勉強時間に関するよくある質問に答えます。
試験日まで○か月。毎日の学習時間は?
たとえば学習を開始した日から試験日まで残り4か月の場合、日々の学習時間は何時間確保すれば良いでしょうか。5か月の場合は? 6か月の場合は?
必要な学習時間を300時間とみなす場合と400時間とみなす場合とに分けて参考値を示します。まずは一般的的な基準である300時間の学習時間を達成するための日々の学習時間は次の表の通りです。
| 試験日まで○ヶ月 | 日々の勉強時間 (300時間目標) |
|---|---|
| 1ヶ月 | 10時間 |
| 2ヶ月 | 5時間 |
| 3ヶ月 | 3時間20分 |
| 4ヶ月 | 2時間30分 |
| 5ヶ月 | 2時間 |
| 6ヶ月 | 1時間40分 |
| 7ヶ月 | 1時間26分 |
| 8ヶ月 | 1時間15分 |
| 9ヶ月 | 1時間7分 |
| 10ヶ月 | 1時間 |
| 11ヶ月 | 55分 |
| 12ヶ月 | 50分 |
試験日まで残り1か月なら、毎日10時間勉強することで300時間を達成できます(あまり現実的ではないかもしれませんが)。試験日まで残り3か月なら毎日3時間20分です。
試験日まで残り6か月なら毎日1時間40分の学習で300時間を達成できます。試験日まで残り9か月なら毎日1時間7分です。これくらいならやろうと思えばやれそうな気がします。
次に今回私が推奨した400時間の学習時間を達成するための日々の学習時間は次の表の通りです。
| 試験日まで○ヶ月 | 日々の勉強時間 (400時間目標) |
|---|---|
| 1ヶ月 | 13時間20分 |
| 2ヶ月 | 6時間40分 |
| 3ヶ月 | 4時間23分 |
| 4ヶ月 | 3時間20分 |
| 5ヶ月 | 2時間40分 |
| 6ヶ月 | 2時間13分 |
| 7ヶ月 | 1時間54分 |
| 8ヶ月 | 1時間40分 |
| 9ヶ月 | 1時間29分 |
| 10ヶ月 | 1時間20分 |
| 11ヶ月 | 1時間13分 |
| 12ヶ月 | 1時間7分 |
試験日まで残り1か月なら、毎日13時間勉強することで400時間を達成できます(到底できそうにありませんが…)。試験日まで残り3か月なら毎日4時間23分です。
試験日まで残り6か月なら毎日2時間13分の学習で400時間を達成できます。試験日まで残り9か月なら毎日1時間29分です。毎日1~2時間なら何とか捻出できる人も多いのではないでしょうか。
* * *
フルタイムで働いている人は「毎日何時間も勉強する時間はとれない」と思われるかもしれません。その場合は平日は少なめの勉強時間におさえて休日にガッツリ勉強すると良いでしょう。
たとえば「本来は毎日2時間勉強する必要がある」とします。でも平日5日間はあまり時間がとれないので半分の1時間だけ勉強し、代わりに土曜日に4.5時間、日曜日に4.5時間勉強するのです。そうすればトータルでは毎日2時間勉強したのと同じ計算になります。
私自身も休日に比重を置いた学習をすることで辻褄を合わせていました。この考え方を採ると学習計画が立てやすいのでおすすめです。
宅建試験の試験日は例年10月の第3日曜日です。試験日については試験日と合格発表日までのスケジュールの記事で詳しく解説しています。

どういう時間配分で勉強したらいいの?
おすすめ勉強法の記事でお伝えした通り、私自身は次の比率で時間を配分しました。
- テキスト学習
- 180時間
- 過去問演習
- 130時間
- 予想問演習
- 100時間
反省点はテキスト学習に時間をかけ過ぎたことです。この反省を活かしてもう1度宅建試験の勉強をゼロからやるとしたら次の割合で時間を配分すると思います。
- テキスト学習
- 100時間
- 過去問演習
- 150時間
- 予想問演習
- 150時間
科目ごとの勉強時間は?
宅建試験の科目(宅建業法・権利関係・法令上の制限・税その他)ごとの勉強時間の目安を知りたい人も多いと思います。科目に関しては人それぞれ得意不得意があるので、一律にこの配分が良いと結論づけることは難しいです。
とはいえ「本試験における科目ごとの問題数」は毎年ほぼ一定であることから問題数の配分と同じ比率で学習するというのが合理的な基準のひとつになります。科目ごとの問題数と全問に占める割合を一覧にすると次の通りです。
| 科目 | 問題数 | 比率 |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 40% |
| 権利関係 | 14問 | 28% |
| 法令上の制限 | 8問 | 16% |
| 税その他 | 8問 | 16% |
| 合計 | 50問 | - |
一般的に必要だと言われている300時間を上記の比率で按分することを考えてみましょう。たとえば宅建業法は全出題の40%を占めているので、300時間のうちの40%である120時間勉強すると考えます。他の科目も含めて一覧にすると次の通りです。
| 科目 | 時間配分 |
|---|---|
| 宅建業法 | 120時間 |
| 権利関係 | 84時間 |
| 法令上の制限 | 48時間 |
| 税その他 | 48時間 |
| 合計 | 300時間 |
他方、私がこの記事で推奨した400時間を先の比率で按分すると次の通りです。
| 科目 | 時間配分 |
|---|---|
| 宅建業法 | 160時間 |
| 権利関係 | 112時間 |
| 法令上の制限 | 64時間 |
| 税その他 | 64時間 |
| 合計 | 400時間 |
上の表をベースにしつつ、たとえば得意科目に関しては時間を減らす、不得意科目は時間を増やす等の調整をしてみると良いと思います。
最短の勉強時間は?
人によっては100時間未満の学習で合格する場合があります。しかしそれはその人がもともと既に十分な予備知識を持っている特殊なケースだったりします。たとえば法学部の出身の人の場合は100時間の勉強で合格しても不思議はありません。
予備知識を持っていない人が100時間の勉強で合格することもあります。しかしそれは本試験で適当にマークしたものがたまたまどれも正解していて、合格基準に到達してしまったというまぐれ合格のケースだったりします。
ネットで「100時間で合格!」とか「直前1週間勉強するだけで合格!」といった謳い文句を見かけるとついそちらに興味を持ってしましますが、実態はそんなものです。
宅建の知識を持っていない人がゼロから勉強して合格するのに必要な勉強時間は一般的には300時間。私の推奨は400時間。最短の勉強時間という意味でもこの答えは変わりません。
他の資格の勉強時間と比較すると?
宅建と他の国家資格・公的資格の勉強時間を比較すると次の表の通りです。
| 資格名 | 必要な学習時間(時間) |
|---|---|
| 司法書士 | 3000 |
| 不動産鑑定士 | 3000 |
| 1級建築士 | 1500 |
| 中小企業診断士 | 1000 |
| 社労士 | 1000 |
| 行政書士 | 800 |
| マンション管理士 | 700 |
| 2級建築士 | 700 |
| FP1級 | 600 |
| ケアマネ | 400 |
| 通関士 | 350 |
| 宅建 | 300 |
| 旅行業務取扱管理者(総合) | 300 |
| 管理業務主任者 | 300 |
| 簿記2級 | 300 |
| FP2級 | 300 |
| 基本情報技術者 | 200 |
| 貸金業務取扱主任者 | 200 |
| 旅行業務取扱管理者(国内) | 200 |
| 簿記3級 | 150 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 100 |
| FP3級 | 100 |
注:数値はおおよそのものだと考えてください。
上の表を見ると宅建試験の300時間あるいは400時間という勉強時間は他の資格試験との比較でみれば特に多いわけではなく、極端に少ないわけでもないことがわかります。
通信講座の勉強時間は?
フォーサイト宅建士講座やユーキャン宅建士講座といった通信講座を利用する場合、一般的に独学よりも学習時間が短くて済みます。通信講座ではできる限り短い時間で効率よく学ぶことを重視して教材・カリキュラムが作成されているからです。
具体的にどのくらい短くできるのかは正直言って人によります。ただ実際に複数の通信講座を受講した私の体感では少なくとも50時間くらいの短縮は期待して良いと思っています。
私が実際に受講した通信講座は次の5つです。
それぞれレビュー記事を書いています。上記リンクをタップしていただければ各講座のレビュー記事一覧に移動できますので参考にしてみてください。
この記事のまとめ

今回は宅建試験の合格に必要な勉強時間についてお伝えしました。この記事の要点を復習すると次の通りです。
- 一般的に宅建試験の合格に必要な勉強時間の目安は300時間だと言われている
- しかし本気で合格したいのなら400時間勉強するのが望ましい
- なぜなら皆が300時間勉強する中で自分の合否を運に左右されないためにプラス100時間勉強するのが有効だからである
慣れない勉強を毎日何時間もするのは確かに大変です。でも宅建資格を取ることができれば就職や転職、昇進・年収アップといった将来の豊かな生活につながります。合格を目指して少しずつ取り組んでいきましょう。
以上、参考になれば嬉しいです。
* * *
次回は宅建と比較されることの多い資格のひとつである管理業務主任者について、宅建とのダブル受験をするべきかどうか検討します。次のブログカードをタップすると移動できます。