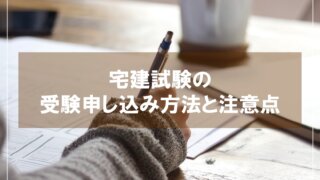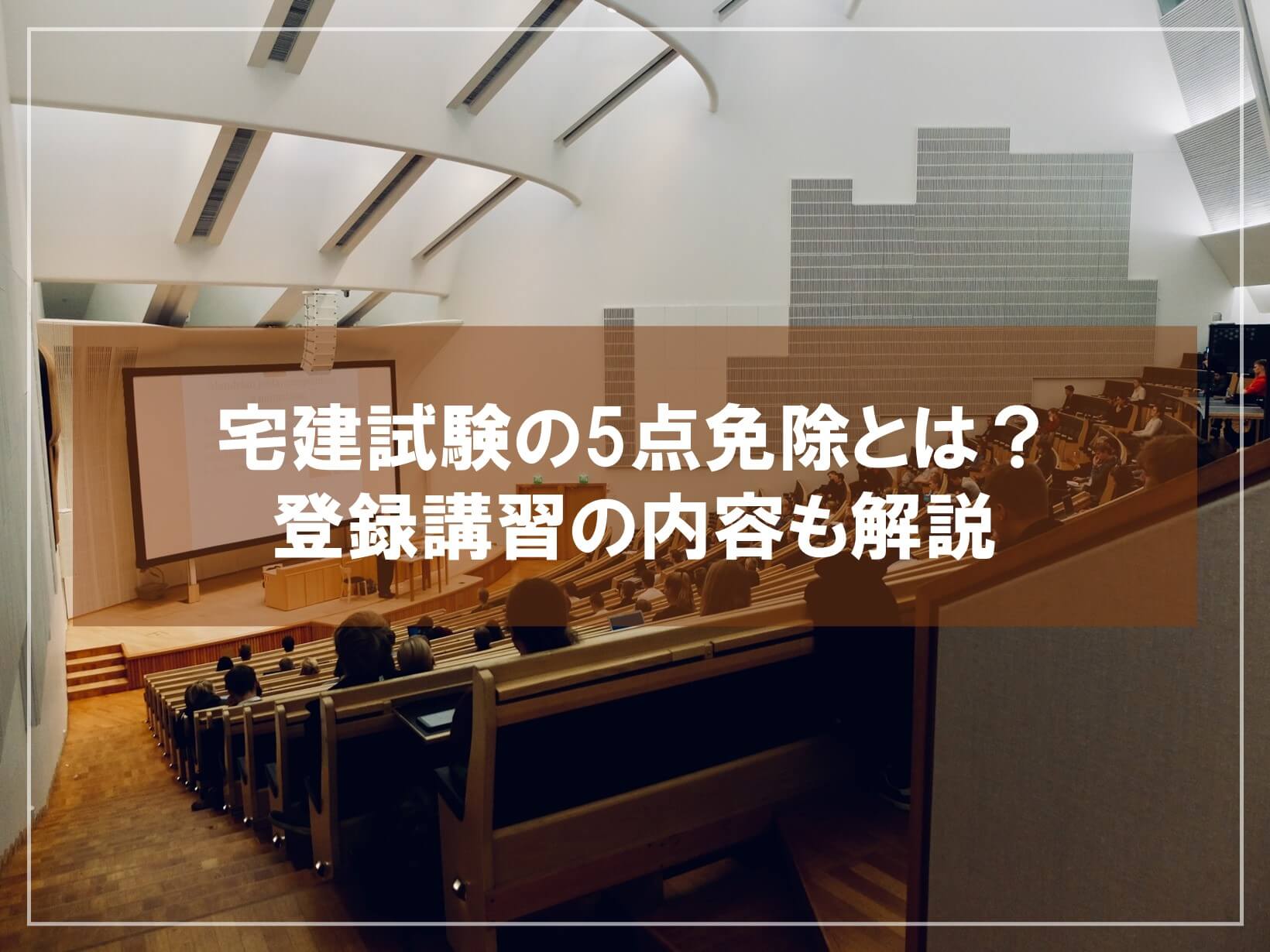宅建試験一発合格済みの宅建士杉山貴隆です。
宅建試験の合格をお金で買えるとしたらあなたは買いますか? もちろんそんなことは現実にはできませんが、宅建試験の「点数を買う」ことならできるかもしれません。
今回は宅建試験の5点免除制度(5問免除制度)と登録講習について解説します。5点免除は一定の条件を満たすことで宅建試験が5点分有利になるという裏技・チート的な制度です。
「知らなかった!」という人はこの記事で概要を知っていただければと思います。「知ってた!」という人もこの記事の後半で料金の安い登録講習実施機関やスクーリングが1日で終わる登録講習実施機関を紹介していますので参考にしてみてください。
5点免除に関する4つのポイント
宅建試験の5点免除に関して今回私が最もお伝えしたいポイントは次の4点です。
- 宅建試験の5点免除とは一定の講習(登録講習)を受講し修了することにより、試験問題5問分の免除が受けられる制度である
- 1点2点の差が合格・不合格の分かれ目になる宅建試験において、5点免除の効果は非常に大きい
- 一般受験者に比べ5点免除対象者のほうが宅建試験の合格率が高い
- 不動産会社で働いている人は大手資格スクール等に申し込むことで登録講習を受けられる
以下で詳しくお伝えします。
5点免除とは?
宅建試験の5点免除とは一定の講習を受講し修了することにより宅建試験の5問分の免除が受けられる制度です。
宅建試験では一般の受験者は出題される50問全部を解かなければなりません。でも講習を終えた5点免除対象者は50問のうちの最後の5問(第46問~第50問)が免除されます。
5問分の免除であることから「5問免除」とも呼ばれます。5点免除の対象者はこの5点分については満点を取ったのと同じ効果が得られます。
「ふ~ん。5点もらえるのは嬉しいけど、たったの5点だし、そんなにすごいの?」「5点くらいなら、別に講習受けなくてもいいんじゃ?」
そんなふうに思う人もいるかもしれませんが、講習を受けられる人は絶対に受けて修了しておくべきです。なぜそう言えるのかを以下で詳しく説明していきます。
5点免除の効果
話の前提として5点免除対象だとどういう効果が得られるのかを具体的に確認しておきましょう。たとえばAさんという一般受験者がいたとします。
Aさんは宅建試験を受験しました。その結果、第1問から第45問の間で30問正解し、第46問から第50問の間で3問正解し、合計でAさんの得点は33点でした。ここでもし合格ラインが35点だったとするとAさんは残念ながら不合格となってしまいます。
次にAさんと全く同じ能力を持ったBさんがいたとして、Bさんが5点免除対象者だったらどうでしょうか。
BさんはAさん同様、第1問から45問の間で30問正解します。一方で第46問から50問については免除され、全部正解したのと同じことになります。
したがってBさんの得点は35点に相当します。ここでもし合格ラインが35点以上だとするとBさんは合格を勝ち取れます。
まとめると、能力が全く同じ2人ですが一般受験者のAさんは不合格となり、5点免除対象者のBさんは合格という結果になりました。これが5点免除の効果です。本来の実力が合格点を下回っていても、強制的に5点分追加できるので合格できることがあるのです。
上記は5点免除の効果をわかりやすく伝えるため話を少し単純化して説明しています。単純化しなかった場合についても解説します。
厳密に言うと5点免除対象のBさんの得点は35点ではなく30点とみなされます。つまり解かなかった5問については得点にカウントしません。「えっ、それならBさんは不合格?」と思うかもしれませんが、そうではありません。
例年、一般受験者の合格基準(たとえば35点以上)から5点を差し引いた5点免除対象者の合格基準(たとえば30点以上)が設定され、5点免除対象者の合否は後者に従って判定されます。
Bさんは5点免除対象者の合格基準を基準を満たしているので合格します。
5点免除制度を利用するべき理由1
5点免除の制度を利用するべき理由の1つめは1点2点の差が合格・不合格の分かれ目になる宅建試験において5点免除の効果が絶大であることです。
先にみたAさんの得点は33点で、合格点に2点足りませんでした。宅建試験ではこのように合格基準点に1~2点足りず涙を飲む人が毎年とてもたくさんいます。
その一方、5点免除の適用を受けると問答無用で5点まるごと得点できるのと同じです。死に物狂いで勉強した一般の受験生がとれるかどうかわからない5問分の得点を、5点免除対象者になれば確実にとれます。
1点差・2点差が運命を分けてしまうところに5点もの強力なアシストを得られるのですから、これを見逃す理由はないでしょう。
5点免除制度を利用するべき理由2
5点免除の制度を利用するべき理由の2つめは事実として一般受験者よりも5点免除対象者のほうが宅建試験の合格率が高いことです。
宅建試験の合格率は例年15%前後ですが、これは一般受験者と5点免除対象者を区別しなかったときの数値です。では一般受験者と5点免除対象者を分けるとどのくらい違うのでしょうか。
実は一般受験者の合格率が14%前後であるのに対し、5点免除対象者の合格率はほぼ毎年20%を上回っています。5点免除対象者のほうが合格率が高いという事実からも5点免除制度をぜひ利用するべきだと言えます。
一般受験者と5点免除対象者の合格率の詳細は宅建試験の合格率まとめ記事でグラフ・表を交えてお伝えしています。ぜひチェックしてみてください。
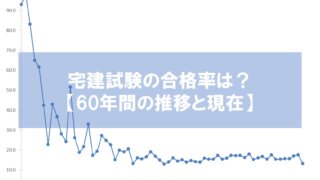
5点免除を受ける方法
では5点免除を受けるにはどうしたら良いのでしょうか? 次の2つのステップが必要です。
- ステップ1
- 登録講習を修了する(登録講習修了者証明書の交付を受ける)
- ステップ2
- 宅建試験に申し込む際、一般受験者ではなく登録講習修了者として申し込む
ステップ2は単に申し込み時に登録講習修了者を選んで申し込むだけの話です。なので5点免除の実質的な要件はステップ1の登録講習のみだと考えて良いでしょう。ここから先は登録講習について解説します。
登録講習とは?
登録講習は宅地建物取引業法第16条第3項に基づき実施される講習であり、修了することで5点免除の資格が得られます。
登録講習は国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施します。講習機関の一覧はこちら。
リンク先の一覧を見ると、LEC・TAC・総合資格・日建学院といった大手資格スクールが目立つことがわかります。
受講資格
登録講習は簡単に言うと不動産会社で働いている人だけが受講できることになっています。もう少し正確に言うと次の通りです(LECの登録講習受講要件から引用)。
登録講習の申込時からスクーリング最終日までの間、宅地建物取引業に従事し、有効な宅建業従業者証明書を所持・携帯・提示できる方が受講可能です。
現在不動産会社に勤めている人は従業者証明書を持っていると思いますので受講できます。現在不動産会社に勤めていない人はアルバイトや派遣という形でも良いので何とか不動産会社にもぐりこめないかを検討してみてください。
「登録講習を受講できるのは不動産業界に携わっている人だけ」なので、5点免除制度も不動産業界に携わっている人しか利用できません。ここでなぜ業界の中の人じゃないとダメなんて条件があるのだろうと不思議に思った人もいるのではないでしょうか。
その答えを端的に言うと5点免除の制度が不動産業界のレベルアップと消費者保護を狙った制度だからです。
これまで不動産業界内の人材の質は何度も問題視されてきました。業界人でも不動産取引関連の法律に対する意識が低く、そのため消費者保護も進まず、また業界内で宅建資格を持った人の数も国が期待したほどには増えなかったのです。
そこで「講習を受講すれば5点やる!だからちゃんと法律を勉強してくれ!そして宅建試験に合格してくれ!」ということで、この5点免除の制度が創設されました。制度を利用する人は「不動産業界人の不勉強さ」に感謝しましょう…笑
講習のスケジュールと内容
登録講習がどのくらいの期間、どんな日程で行われるかというと次の通りです。
- 2ヶ月程度の通信講座
- 自宅に届く通信教材(テキストなど)を使って自主学習を進める
- 2日間のスクーリング
- 講習会場で講義を受ける(スクーリングとは「スクールに行く」つまり通学という意味)
- 修了試験
- スクーリング2日目の最後に実施されるテストを受ける。出題範囲は通信講座の内容およびスクーリングの内容
通信講座を終えてスクーリングに全日参加し、かつ修了試験に合格した場合登録講習修了者証明書を受け取ることができます。
講習全体で学習する内容は次の通りです。
- 宅地建物取引業法その他関係法令に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
- 宅地及び建物の需給に関する科目
- 宅地及び建物の調査に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目
この一覧からわかるように登録講習では5点免除によって免除される5問の範囲(統計や土地・建物)だけを学ぶのではなく、それ以外の不動産取引にまつわるさまざまなことを合わせて学ぶことになっています。
修了者証明書の有効期限
登録講習修了者証明書には3年間の有効期限があります。たとえば今年登録講習を受けて修了し、5点免除で受験したものの不合格だった…という場合でも、来年と再来年は同じ証明書で5点免除を受けられるのが原則です。
講習の費用
登録講習の受講料金は実施期間によって異なります。相場は10,000円から20,000円です。20,000円を超えるとちょっと高い感じがします。
不動産会社によっては従業員が登録講習を受ける際の費用を会社負担にしてくれる場合があります。そういう制度が無いかどうか勤め先に確認してみてください。
講習修了の難易度
「登録講習の修了試験が難しかったらどうしよう?」と心配する人もいると思いますが、簡単なので大丈夫です。
というのも修了試験には通信講座やスクーリングで学んだ内容をベースとした基本的な事項が出題されます。しかも講習会場の講義では講師が「ここは重要だから線を引いてね!メモしてね!」などと言ってくれます。
なので最低限そういう強調された部分をおさえておけばOK。真面目に受講したのに不合格になってしまうことはほぼありません。
申込期間・講習実施期間
登録講習の申し込み時期は実施期間によって異なりますが、12月頃から開始し6月には締め切られることが多いです。
講習そのものは3月頃から7月頃までやっています。宅建試験の申し込み時期が7月なので、それまでには登録講習修了証明書を持っておけるよう早めに申し込みましょう。
主な申し込み先
登録講習の主な申し込み先をピックアップしておきます。
よくある質問
5点免除・登録講習に関するよくある質問に答えます。
料金が安い登録講習実施機関は?
登録講習の料金は私が調べた範囲だと次のところが安いです(2022年度実績)。
- プライシングジャパン(東京のみ)
- 11,000円(税込)
- 総合資格学院(全国)
- 早期割引料金12,500円(税込)
通常料金16,000円(税込) - 日建学院(全国)
- 15,000円(税込)
登録講習の修了要件は?
登録講習の修了要件はたいていは次の2要件です。
- スクーリングの全日程に参加すること
- 修了試験で基準以上の点数をとること(基準点は講習実施機関による)
詳しくは講習実施機関のサイトで確認してください。
免除対象になる5問の内容は?
5点免除対象者が宅建試験において免除される5問の内容は次の通りです。
- 問46
- 住宅金融支援機構に関する出題
- 問47
- 景品表示法に関する出題
- 問48
- 統計に関する出題
- 問49
- 土地に関する出題
- 問50
- 建物に関する出題
問題例を見てみたい人は税・その他科目の範囲と問題例の記事で過去問をいくつかピックアップしています。チェックしてみてください。
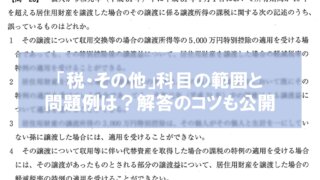
免除対象者の点数配分は?
5点免除対象者の場合、宅建試験は通常より5問少ない45問となります。科目ごとの配分は例年通りであれば次の通りです(1問1点、45点満点)。
| 科目名 | 配分 |
|---|---|
| 宅建業法 | 20問(20点) |
| 権利関係 | 14問(14点) |
| 法令上の制限 | 8問(8点) |
| 税・その他 | 3問(3点) |
5点免除対象者の試験内容・試験時間は変わる?
5点免除対象者の試験内容は免除対象の5問が無いこと以外は一般受験者と同じです。
試験時間は一般受験者より10分短くなることが通例となっています。試験時間と時間配分の記事も参照いただければと思います。

5点免除で宅建試験に落ちた場合は?
5点免除対象の人でも宅建試験の合格基準点に届かず不合格になる場合があります。実のところ5点免除対象の人の合格率は20%を少し超える程度です。一般受験者より合格しやすいのは確かですが、それでも7~8割の人は落ちています。
登録講習を受けたからといって気を抜かずに学習を続けましょう。なお、落ちたからといってペナルティは無く、余分な手続きなども特にありません。
もう7月なんだけど今から登録講習に申し込める?
かなり難しいですが、申し込みできる機関を探せば見つかるかもしれません。探しましょう。
スクーリングを1日で終えたい
実施機関によっては1日で終わるスクーリングを実施しているところもあります。たとえば日本宅建学院は通常の2日間にわたるコースの他に1日コースを設けています(会場は主に東京・大阪。2022年度実績)。
また株式会社おおうら(自習室うめだ)のスクーリングはどの日程でも1日のみです(会場は大阪梅田・東京四谷、2022年度実績)。
住んでいる地域の登録講習を受けたい
「東京の登録講習」「大阪の登録講習」「名古屋の登録講習」「仙台の登録講習」「福岡の登録講習」といった情報を探す人は多いようです。できることなら住んでいる場所から近いところで講習を受けたいですよね。
大手の資格スクールなら全国各地の地域校で登録講習を実施しています。ぜひ調べてみてください。
この記事のまとめ

今回は宅建試験の5点免除についてお伝えしました。この記事の要点を復習すると次の通りです。
- 宅建試験の5点免除とは一定の講習(登録講習)を受講し修了することにより、試験問題5問分の免除が受けられる制度である
- 1点2点の差が合格・不合格の分かれ目になる宅建試験において、5点免除の効果は非常に大きい
- 一般受験者に比べ5点免除対象者のほうが宅建試験の合格率が高い
- 不動産会社で働いている人は、大手資格スクール等に申し込むことで登録講習を受けられる
5点免除を受けることで合格する可能性をグッと引き上げることができます。それにかかるコストは登録講習の受講時間と費用ですが、5点ももらえるなら十分割に合う投資です。不動産会社に勤めている人は必ず受講しましょう。
以上、参考になれば嬉しいです。
* * *
次回は宅建試験の受験申し込み方法と注意点について確認していきます。下のブログカードをタップすると移動できます。