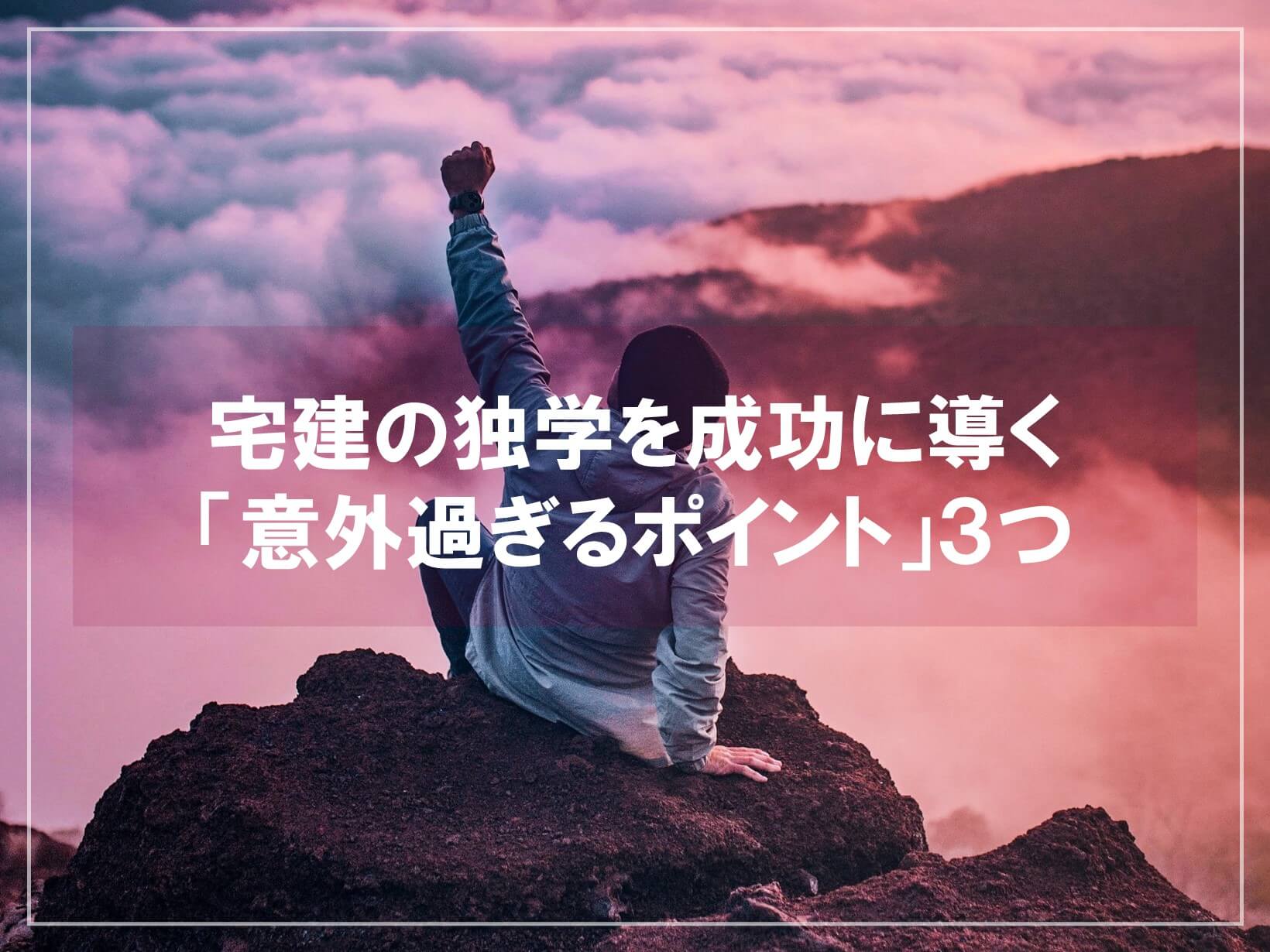宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。
今回は宅建の独学を成功に導く3つのポイントをお伝えします。私が実際に独学した経験から得た宅建独学のカナメです。
あなたは3つのポイントを知ることで独学者が陥りやすい失敗を回避できます。ぜひ参考にしてみてください。
宅建の独学を成功に導く「意外過ぎるポイント」3つ
宅建の独学を成功に導くポイントは、次の3点です。
- 過去問をあてにしない
- 合格点(合格ライン)を狙わない
- 合格をゴールにしない
上記の内容を見て意外に思う人は多いと思います。宅建の独学といえば「過去問重視」「合格点を取れればOK」「ゴールとして目指すものは当然、試験合格」と考えるのが一般的であり、それとは真逆のことを言っているからです。
しかし私は上記の3つのポイントが宅建の独学を成功に導く真理であることを確信しています。なぜそう言えるのか、以下で詳しく説明していきます。
【ポイント1】過去問をあてにしない
宅建の独学を成功させるポイントの1つめは過去問をあてにしないことです。
「でも宅建の試験って過去問の焼き直しが大半って聞いたよ? なのに過去問をあてにしないってどういうこと?」
そう疑問に思いますよね。もちろん過去問を勉強するなということではありません。よく言われているように過去問の繰り返しは宅建試験の攻略において非常に大切です。
では「過去問をあてにしない」とはどういう意味なのか? 「過去問を死ぬほど反復すれば合格できる」といった考えを捨てるということです。
なぜなら過去問をマスターする作業は本気で合格したい人なら皆やるから。私の見立てでは全受験者の3割くらいはきっちり過去問をマスターして受験しています。
言い換えると、100人の受験者がいたらそのうち30人は過去問をみっちり勉強してくるだろうだろうことです(逆に、残り70人は過去問もまともにできていないと思います。私の主観ですが)。
一方、宅建試験の合格率は毎年15%程度。100人の受験者がいたら15人しか合格しません。そしてその15人は当然ながら過去問をマスターした30人の中から輩出されます。結局過去問をマスターしている人のうち実際に合格できるのは半分だけなんです。
* * *
このように考えていくと、あなたが独学するにあたって過去問だけ繰り返していてはダメだということがわかると思います。過去問演習後のもうひと頑張りが合格するためには不可欠です。
その「もうひと頑張り」とは何か? 当ブログでは繰り返しお伝えしていますが予想問演習(市販の予想模試)です。
例年、6月~7月頃になるとLECやTACが予想模試を書店やAmazonで販売します。1冊2,000円ほどの価格で試験3回分(150問)くらいの問題が収録されています。
私のおすすめはこういった予想模試を試験6~9回分くらいマスターしておくことです。そうすることで「過去問をマスターしたけど合格するかはわからない30人」から「過去問も予想問もマスターして最も合格する可能性の高い15人」にレベルアップできます。
予想模試を併用する考え方については本当に必要な試験対策の記事でも解説しています。ぜひチェックしてみてください。

【ポイント2】合格点(合格ライン)を狙わない
宅建の独学を成功させるポイントの2つめは合格点(合格ライン)を狙わないことです。
「えっ 宅建試験に合格するには合格点を取らないといけないでしょ?」「それなら、合格点は当然狙うべきでは?」
このように思われたかもしれません。でも宅建試験は「合格点くらいの点数を狙っていると、なぜか合格点から1~2点低い点数を取ってしまい不合格になる」、そういう試験です。そう言われても意味がわからない人もいると思うのでもう少し説明します。
まず宅建試験の合格点は毎年変わります。しかも合格基準点は試験実施前には決まっていないというのが定説です。試験実施後、受験者全体の上位の15%程度が合格者になるように合格基準点が決定されていると見られています。
なお合格基準点が公表されるのは合格発表のときであり、点数としては50点満点中33点~35点くらいの点数になることが多いです。
さて合格点が「50点満点中33点~35点くらいの点数になることが多い」ということをもって、35点、つまり50点満点中の7割得点すれば良いという指導をしている資格学校や通信講座がたくさんあります。でもそれじゃダメなんです。
上位15%程度しか合格者になれないという試験の構造上、非常に多くの受験者が合格点より1点~数点低いところに集中するはずですから。
実際、わずかに合格点に届かなかったということで涙を飲む受験者が毎年大勢います。要するにあなたが合格点を目指して独学しても、合格点に到達できない可能性が非常に高いんです。
ではどうすれば良いか? 答えは合格安全圏だと思われる40点台を狙うことです。最初から40点台を目指していれば、たとえ得点が目標より1~2点低くなったとしても合格点以上の点数を取ることができます。
実際に40点台をとるのはなかなか大変ですが、過去問と予想問を何度も回して習得すれば得点可能だと私は考えています。実際、私自身は40点取れました。ケアレスミスが無ければ、もう2点良い点数だったほどでした。
あなたは合格点を狙うのではなく合格安全圏の40点台を狙うことで独学合格を大きくたぐり寄せることができます。
40点台を狙う具体的な方法についてはおすすめ宅建独学勉強法の記事で解説しています。あわせてチェックしてみてください。

【ポイント3】合格をゴールにしない
宅建の独学を成功させるポイントの3つめは合格をゴールにしないことです。
「いやいや!宅建試験に合格するのが最終ゴールのはず。何言ってんだ!」
と思われたかもしれませんが、もう1度考えてみてほしいです。あなたにとって宅建の合格はゴールではないはず。むしろ宅建資格をとったあとに実現したい何かが本当のゴールですよね? たとえば…
- 現職の会社から宅建手当をもらって年収アップ
- 宅建取得をアピールして昇進につなげる
- 宅建を転職に活かしてもっと好待遇で将来性のある環境で働く
- 宅建を取った後不動産会社を立ち上げて大きく稼ぐ
こういった今よりも幸せな未来を実現することが本当のゴールのはずだと思います。宅建の独学を成功させるためにそこを常に意識していてほしいのです。
もしあなたが「宅建試験の合格こそが自分のゴールだ」と思い込んでしまうと、あなたは消耗しやすくなります。なぜなら宅建の独学ってものすごく地味で地道だから。
テキストを読了するため毎日ひたすら黙って読む。過去問を淡々と12年分解く。1周したら淡々ともう1周。それが終わったら淡々ともう1周。過去問はそろそろ大丈夫そうだと思えたら、次は予想模試を淡々と解き続ける。1周終わったらまた1周。もう1周…
膨大な時間と精神力を投下することになります。それでいて合格するかどうかは、究極的には受験するまでわかりません。これでは消耗するなというほうが無理です。
* * *
そんな辛く苦しい日々を覚悟する必要がある独学ですが、心の中に「今よりも幸せな未来」を描けていると頑張れます。
今この瞬間は大変だけれど、きっと苦労は報われるはず。この道を進んでいけば明るくて楽しい場所にたどり着けるはず。一筋の希望があるだけで、不思議と明日も明後日も、その次の日も頑張れるんです。
以上をまとめると、宅建試験の合格はただの手段。あなたにとってゴール(目的)ではありません。本当のゴールはあなた自身がよく知っているはず。資格取得後の未来を見据えつつ、その実現のために学習を進めていきましょう。
全身全霊をかけて宅建の独学に打ち込むと、時にはどうしても疲れて立ち止まりたくなります。そんなときは少し休んでリフレッシュすることが大切です。
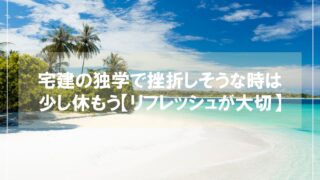
この記事のまとめ

今回は宅建の独学を成功に導く「意外過ぎるポイント」3つというテーマでお伝えしました。3つのポイントを復習すると次の通りです。
- 過去問をあてにしない
- 過去問を極めるだけでは足りない。予想問をマスターしよう
- 合格点を狙わない
- 合格点を狙っていると到達できずに落ちる。合格安全圏を狙おう
- 合格をゴールにしない
- 合格は手段。今よりも幸せな未来をゴールに見据えよう
あなたの宅建独学が成功することを心から願っています。
以上、参考になれば嬉しいです。