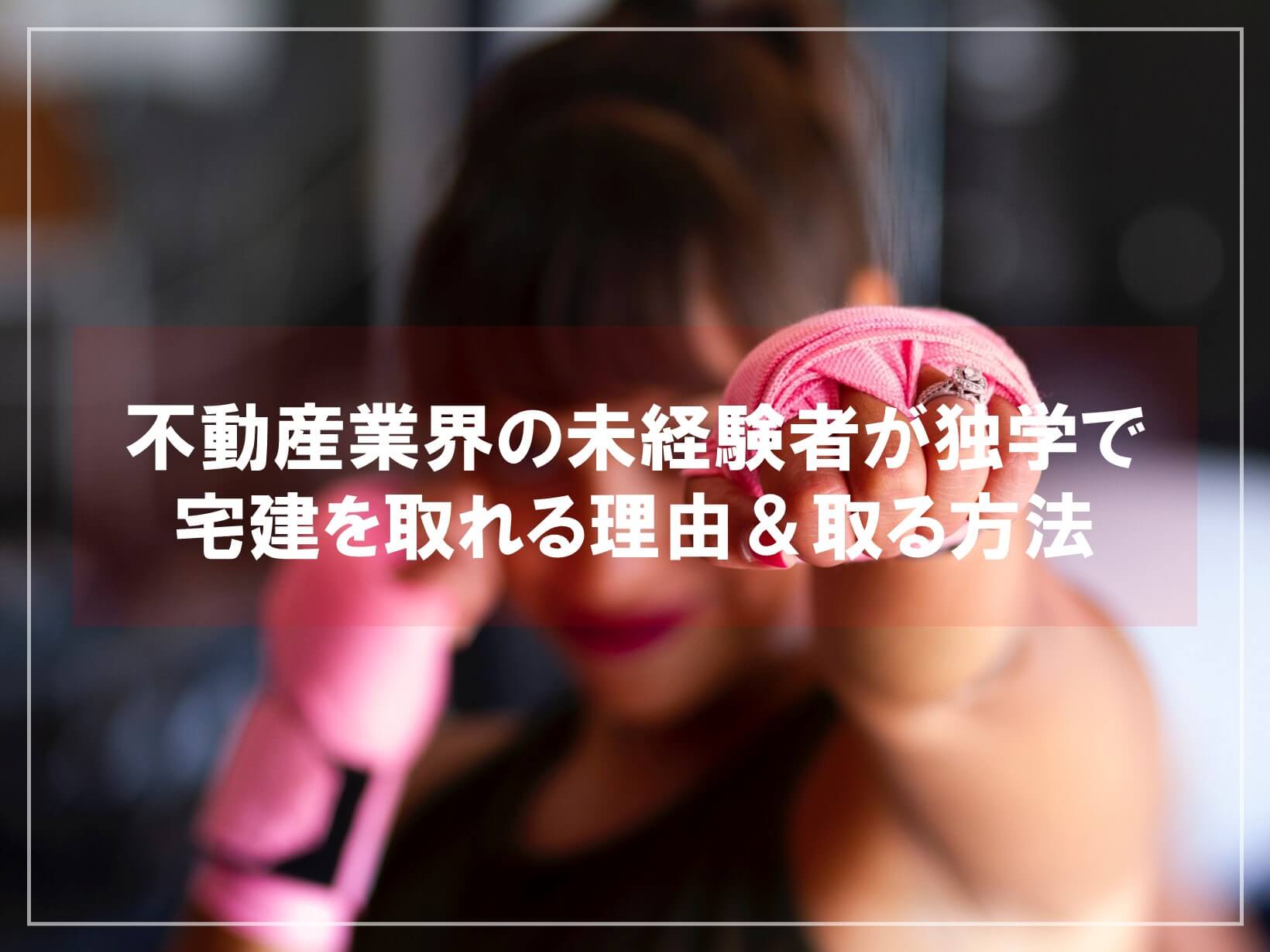宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。
今回は不動産業界の未経験者が独学で宅建を取れる理由とその方法についてお話しします。
宅建試験は受験資格がなく誰でも受験できる試験です。とはいえ「難易度が高いらしいから未経験者が独学しても受からないのでは?」と疑問に思ってしまいますよね。
実はそんなことはないんです。私も学習開始時点では未経験者でしたが独学で受かりましたし、周囲にも未経験で独学し合格した人がいます。そこで私の経験や考えたことをもとに未経験者の独学についてお伝えできることをまとめました。
この記事を最後まで読んでいただくと「経験が無くても宅建試験に独学で合格できそう!」と思っていただけるはずです。ぜひ参考にしてみてください。
未経験者が独学で宅建試験に合格できる理由
不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格できる理由は次の3つです。
- 業界経験者でなければ理解できないような学習事項は無い
- 独学用のさまざまな教材が販売されている
- 学生や主婦が毎年大勢受かっている
以下で順番に見ていきましょう。
業界経験者でなければ理解できないような学習事項は無い
不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格できる理由の1つめは業界経験者でなければ理解できないような学習事項は無いことです。
宅建試験の出題範囲は「民法(権利関係)」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」に大別されます。一見どの範囲も難しそうで、不動産業界に携わっていないと理解できないのではないかと思ってしまいます。
でも実際にはどの範囲の内容も法律の基礎中の基礎くらいの難易度です。不動産関係の仕事を一切したことがない人でも落ち着いてテキストを読んでいけば問題なく理解できます。
むしろ経験者のほうが実務を通じて間違った知識を覚えていて学習の妨げになることがあるくらい。それに比べれば未経験者は「まっさらな状態」から新しい知識を習得しやすいので、有利だと言えます。
* * *
ただし実際の試験問題は簡単には解けないように「ヒネリ」をきかせてあるので注意しましょう。
宅建試験は「落とすための試験」です。合格率を15~17%程度に抑えるため、ヒネった出題で受験生を惑わそうとします。合格点を取りたいのなら、繰り返し過去問を解くといったトレーニングを積んでヒネリに慣れる必要があります。
とはいえヒネリに慣れる必要があるのは業界経験者でも同じこと。要は業界経験者であってもそうでなくても、宅建試験の難易度はそう変わるものではないんです。
実際、私の周囲でも毎年のように業界未経験者が合格していますので、経験が無いことを不安に思う必要はありません。
独学用のさまざまな教材が販売されている
不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格できる理由の2つめは独学用のさまざまな教材が販売されていることです。
世の中にはいろいろな資格がありますが、その中には受験する人が少ないために独学用の教材がほとんど無いような資格もあります。そういう場合は確かに業界未経験者が独学で試験を突破するのは難しいです。
その一方、宅建は国家資格の中でも1、2を争う人気があり毎年20万人もの人が受験しています。そのため宅建の受験対策だけでも一大市場を形成していおり、独学用の教材がたくさん出版されているんです。
私は過去に「宅建試験の独学用テキストを比較する記事」を書いたのですが、そのとき比較しただけでも11種類のテキストがありました(現在は内容を発展させておすすめ・ランキングに頼らず自分でテキストを選ぶための記事になっています)。
独学用のテキストや問題集は業界経験が無く知識ゼロからスタートすることを前提に書かれています。豊富な教材の中から自分にあったものを選んで学べるので、未経験者の独学であっても問題なく合格を目指せると考えてOKです。
学生や主婦が毎年大勢受かっている
不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格できる理由の3つめは学生や主婦も毎年大勢受かっていることです。
もちろん学生さんや主婦の方だからといってその全員が「未経験で独学した人」とは言えません。とはいえ学生さんの場合お金の余裕がない人も多く、業界未経験で独学する人は珍しくないはずです。
また主婦の方についても未経験者がおそらくは大半。そして家計のためにもスクールなどには通わず、独学をするケースがかなりあると思われます。
以上のことから学生・主婦には相当数の「未経験かつ独学」の人が含まれていると考えられるわけです。とすれば、学生・主婦が大勢合格していれば未経験・独学でも合格できることの根拠のひとつになりますよね。
ここで宅建試験の実施団体であるRETIO(不動産適正取引推進機構)が令和元年までに発表した属性別の合格者数を確認してみましょう。まず各年度の合格者のうち学生の数は次の通りです。
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 平成26年度 | 3,543人 |
| 平成27年度 | 2,941人 |
| 平成28年度 | 3,385人 |
| 平成29年度 | 3,747人 |
| 平成30年度 | 3,677人 |
毎年、合格者のうち3,000~3,500人ほどが学生さんであることがわかります。
次に合格者のうち主婦の数は次の通り。
| 年度 | 合格者数 |
|---|---|
| 平成26年度 | 1,336人 |
| 平成27年度 | 1,266人 |
| 平成28年度 | 1,343人 |
| 平成29年度 | 1,288人 |
| 平成30年度 | 1,350人 |
毎年、合格者のうち1,200~1,300人ほどが主婦の方であることがわかります。
学生さんと主婦の方を合わせると毎年4,000人以上が合格しているんです。未経験者が独学で宅建試験に合格することは夢物語なのではなく、十分実現可能な目標なんだということが数字からも見えてきたのではないでしょうか。
未経験者が独学で宅建試験に合格する方法
ここからは不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格する方法を具体的に見ていきます。方法としては次の3ステップです。
- 独学の流れを把握する
- だいたいの学習計画を立てる
- 教材を買って勉強を始める
以下で詳しく見ていきましょう。
独学の流れを把握する
不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格する方法の最初のステップとして独学の流れを把握しましょう。
宅建を受験すると決めた場合「そもそも国家試験を受けるのは初めて」という人が多いと思います(私もそうでした)。国家試験初受験の人の場合は特にそうですが、どうやって勉強を進めていくのがベストなのか、正直言ってわからないですよね。
伝統的には宅建試験の勉強は「テキストを読んで、過去問を繰り返し解く」のが王道の学習方法だとされています。しかし近年の宅建試験の受験生は全体的にレベルが上がっていて、過去問の繰り返し演習だけではやや心もとないです。
そこで私はこのブログで次の学習方法を繰り返し提案しています。
- 1. テキスト学習
- 市販の宅建試験対策の基本テキストを一読する(不足を感じるときはもう1度読む)
- 2. 過去問演習
- 年度別の過去問題集(10~12年分収録)を繰り返し解く
- 3. 予想問演習
- 夏頃に市販される予想模試を少なくとも1冊繰り返し解く
伝統的な「テキスト+過去問」に「予想問」を付け加えた学習法です。私自身、不動産業界の経験が無い状態で学習を始めたのですが上記の方法で一発合格しました。
当ブログの読者の方からも「あなたの方法を参考に独学して宅建試験に合格できました」との報告を複数いただいています。
私が勧める勉強法の詳しい内容はおすすめ宅建独学勉強法の記事をチェックしてみてください。

おおよその学習計画を立てる
不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格する方法の次のステップとしてだいたいの学習計画を立案しましょう。
学習計画といっても複雑で精密な計画を立てるわけではありません。宅建試験の合格に必要とされている「300時間」の学習時間を達成するために1日何時間勉強すればいいのかを考えるだけです。
たとえば宅建試験の本番(例年10月中旬)まで残り4ヶ月間(120日)だとしたら、300÷120=2.5という計算をします。1日あたり2.5時間(2時間30分)勉強すると、試験日までに300時間勉強できるということです。
1日の勉強時間が決まったら、あとは目標達成を毎日積み上げていくことで自然と合格に必要な実力がついていきます。このあたりの考え方は宅建独学の効率化の記事でも詳しく語りましたので、参考にしてみてください。
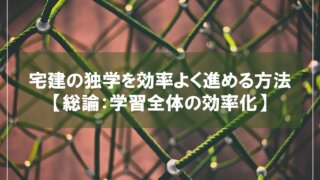
教材を買って勉強を始める
不動産業界の未経験者が独学で宅建試験に合格する方法の最後のステップとして教材を買って勉強を開始しましょう。
「未経験者だけど、合格できるかな…」「いや、やっぱり自分には無理なんじゃないか…」
業界未経験者の方ほどそのように考え込んでしまって、なかなか勉強をスタートできないようです。でもそういう人が多いからこそ、あなたが即座にスタートを切ってしまえばそれだけで有利になれます。
実際、早めに始めたほうが1日あたりの勉強時間も短くて済み、体力的に楽に独学を進められます。また、数か月にわたる学習期間の間には予期していなかった遅れやトラブルも起きることがありますが、そういうことにも余裕をもって対処しやすくなります。
さあ、書店へ行ってテキストだけでもいいので購入して読み始めましょう。スタートしてしまえば、半分くらいは勝ったようなものです。
どうしても自信が持てない場合
「未経験の自分が独学しても合格できる可能性がある、というのはわかった。でも、やっぱり不動産の取引とか法律とかってわからないことだらけだから不安で、自信が持てない…」
そう感じる人もいると思います。対処方法として「未経験」を補う方法と「独学」を補う方法とがあります。
以下で詳しくお伝えしますので、どちらか必要なほう、または両方を実行してみると良いでしょう。そうすると宅建試験の合格が一段と現実的なものになるはずです。
「未経験」を補う方法
「未経験」は宅建入門マンガを読むことである程度補うことができます。宅建入門マンガとは本格的な受験対策の前にざっと宅建試験の内容を把握できるマンガのことです。

日建学院やユーキャンなどいくつかの資格対策講座が宅建入門マンガを毎年出版しています。それらを読むとわかりますが宅建入門マンガでは不動産会社が舞台となっていることが多いです。
なので「不動産取引の現場の雰囲気」や「どういったことが実務上の問題になりやすいのか」といったことがストーリーの中で理解できます。未経験の方にとっては業界内部の雰囲気を知るちょうど良い手掛かりになりますよ。
宅建入門マンガの比較ランキングを用意しています。そちらも参考にしてみてください。

「独学」を補う方法
「独学」はYouTube動画を視聴する、または通信講座を受講することである程度補うことができます。
最近はYouTubeで無料で見られる講義動画が増えてきました。
こういった動画を活用すれば、講師の先生によるわかりやすい授業を金銭的な負担無しで受けられます。動画のコメント欄を見ると「YouTube講義動画のおかげて合格できました」という投稿があったりして期待できそうです。
* * *
少しお金を出しても構わない方は通信講座も検討しましょう。通信講座なら合格実績に裏打ちされた完成度の高い教材を利用でき、それでいて料金は資格スクールよりもずっと安いです。
当ブログでは宅建試験にこれから挑戦する人へ情報を提供するため、複数の通信講座を実際に受講してレビューしました。
その結果、初心者の方にはフォーサイト宅建士講座とスタディング宅建士講座を特にオススメしています。
どちらの講座も無料でお試しできます。興味のある人はまずは無料の範囲で試してみると良いでしょう。
この記事のまとめ

今回は「不動産業界の未経験者が独学で宅建を取れる理由&取る方法」というテーマでお伝えしました。要点を復習しましょう。
まず「不動産業界の未経験者が独学で宅建を取れる理由」は次の3点です。
- 業界経験者でなければ理解できないような学習事項は無い
- 独学用のさまざまな教材が販売されている
- 学生や主婦が毎年大勢受かっている
次に「不動産業界の未経験者が独学で宅建を取る方法」は次の3ステップです。
- 1. 独学の流れを把握する
- テキスト学習→過去問演習→予想問演習
- 2. だいたいの学習計画を立てる
- 1日の学習時間を決めて試験本番までに300時間達成する
- 3. 教材を買って勉強を始める
- 考えたり悩んだりするのをやめて早期にスタートを切ってしまったほうが有利
お伝えしたように、独学で宅建試験に合格する業界未経験者は毎年たくさんいます。そして次はあなたの番です。ゴールを目指して少しずつ前進してください。応援しています。
以上、参考になれば嬉しいです。